|
大福寺時代の大阪仮病院教師・生徒集合写真
[明治2年(1869年)6月] |
|
 |
|
新政府は大阪に病院設立を計画、病院竣工まで仮病院を大福寺に定め、緒方惟準を病院と医学伝習の責任者に任じ、A.F.ボードウインを教師に任命、明治2年2月発足した。
写真は明治2年6月、仮病院から新病院移転に際して大福寺本堂前での記念写真。中央にボードウイン、その前に緒方惟準。
|
|
| 緒方惟準と三人のオランダ教師 |
|
●緒方惟準の行政官辞令(明治2年2月)
政府は新設する大阪仮病院において、緒方惟準に対しボードウインと相談して、病院と医学伝習の業務開始を命じた。 |
|
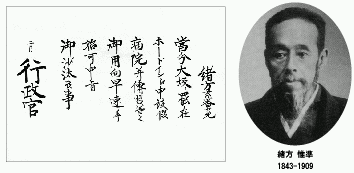 |
|
|
●蘭医A.F.ボードウインの大阪府辞令(明治2年2月)
ボードウインには大阪府の管轄のもと、治療と医学教育の任に当たることを命じた。 |
|
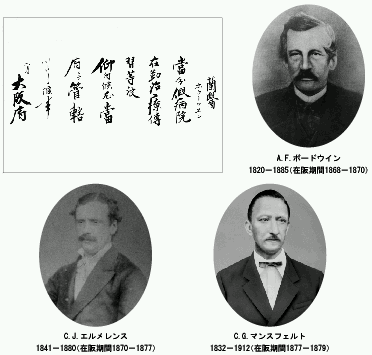 |
|
大阪府医学校病院全景、同正面玄関および
教師と生徒たちの集合写真
[明治2年(1869年)11月―同4年(1871年)] |
|
 |
|
明治2年(1869年)11月大阪府病院を拡張し、ボードウイン設計の華麗なる大阪府医学校病院を開設した。東京の大学校から岩佐純・高橋文貞ら文官・医官・教官・医師ら多数が派遣された。当時の官設医学校は東京府、大阪府、長崎府の3校であった。建造物は明治3年頃ほぼ完成したとみられる。集合写真は同年6月ボードウインと新任教師エルメレンス交代時の記念写真。
|
|
三瀬諸淵(ボードウイン、エルメレンスの通訳)と
シーボルトの孫たか |
|
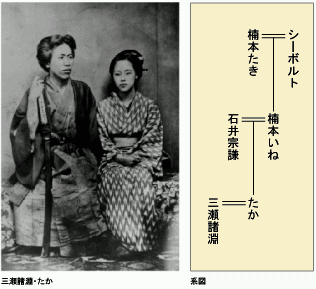 |
|
三瀬諸淵(周三)は語学の才に長じ、数ヶ国語をよくした。医学を二宮敬作、英語を村田蔵六(大村益次郎)、蘭学を川島再助・名村八左衛門に学び、安政6年(1859年)再来したシーボルトの門人となり、幕府対外顧問、元治元年(1864年)宇和島藩お抱えとなり、たかと結婚した。明治3年(1870年)大阪医学校勤務、ボードウイン、エルメレンスの訳官をつとめ、多数の翻訳書を世にだした。
なお、大村益次郎が京都木屋町で遭難の際、ボードウイン、緒方惟準が上京治療にあたり、後大阪府病院に移送され、娘いね、孫たか、三瀬諸淵らの手厚い看護の下におかれたが、その効は実らなかった。
|