音楽の現場は人と人をむすびつける。
そこへ音楽学者が入り込むとき、新しい人間関係が
できて音楽がさらに活性化して、もうひとつ別の
時空間が展開する。
|
|
| 諸民族の音楽を訪ねるフィールドワーク、演奏の仕組や社会的・歴史的背景を調べる民族音楽学、街に出て「社会から学び社会へ還元する」応用音楽学が阪大音楽学の特徴の一つ。 |
|
 |
ミクロネシア離島エウリピック環礁島にて
生まれて初めて自分たちの録音された歌に聴き入る夫婦、子ども、親類。約10年後にはカセットで自ら録音したり、外来の音楽を楽しむようになる。腰布が本来の姿だが、よその島を真似た腰蓑が大きな社会変化を予告している。
山口修撮影、1965年12月。
|
|
|
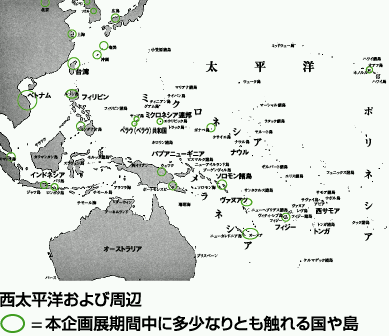 |
|
パプアニューギニア東セピック州マリ社会の
祭礼踊シングシング |
|
 |
客を歓迎する祭礼は、盆踊りにも似た反時計まわりの円舞が特徴。腰蓑やボディペインティングが正装だが、ジャングル奥地にも外来文化が押し寄せている。阪大創立50周年(1981)記念事業は全学部と1研究所による10チーム編成で実施。山口班は国立芸術学校等と連携。音楽や舞踊の種目、楽器の製作工程、社会風習などを記録。その方法は現地側共同研究員と相談してきめ、機材の操作も覚えてもらった。成果はパプアニューギニア学研究所および阪大博物館に保管。
共同研究者トーマス・ワエキ撮影。中央背後に山口。1985年12月。 |
|