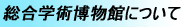  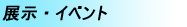 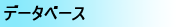  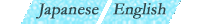 |
Overview 地域に生き、世界に伸びる 大阪大学には、ふたつの源流があります。江戸時代中期に大阪庶民の手で創設され、自由で批判精神に富む学問の花を咲かせた「懐徳堂」と、江戸時代末期、緒方洪庵が創設し明治維新-近代日本創設の原動力となる福沢諭吉をはじめ、若き俊英たちを輩出した「適塾」です。大阪大学はこうした知的伝統の上に。「地域に生き世界に伸びる」をモットーとして、わが国有数の総合大学に発展し、さまざまな分野で日本と世界をリードしています。 収集 大阪大学のすべての学部・研究科および研究所などに残されている貴重な学術標本を収集し、一元的に管理します。さらに集めた標本を学内外の研究教育に活用できるようデジタル情報化し、インターネットを通じて公開できる環境の整備を進めています。また、貴重な学術標本の劣化や損傷を防ぎ、恒久的に保存するための技術開発に関する研究などもおこないます。 活用 最先端の分析・測定技術を駆使して、標本資料の新しい学術価値を見出します。同時に、これらの資料を通じ、異なる学問分野の間で共同研究のコーディネーター役を果します。また、古い理化学機器などの学術標本を、教育活動へ有効的に再活用する方法穂研究します。さらに、企画展を通じて、大阪大学が生み出す最新の研究教育の成果をわかりやすく社会に還元します。 展示 常設展示 : 豊中キャンパスの理学部建設現場から出土したワニの化石(マチカネワニ)の復元骨格、日本各地で収集された岩石標本を展示しています。今後、待兼山の地下に眠る古墳などから出土した土器や待兼山の自然をテーマとした常設展示を充実させていく予定です。 秋の企画展 : 毎年10月に開催を予定。大阪大学の研究教育成果の発信の場として、研究者自らが自分の研究成果を地域社会の皆様にもわかるように紹介します。 サイバーミュージアム : 学術標本の画像データベース化とインターネットによる公開を柱に、学内外の多くの方々に大阪大学が所有する貴重な標本情報をご利用いただけるシステム作りを目指します。 |

