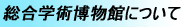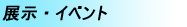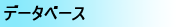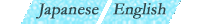サイエンスカフェ@待兼山
大阪大学総合学術博物館で、サイエンスカフェを楽しみませんか。コーヒーを片手にゆったりとした雰囲気で、「科学する」とはどういうことか、研究者とともに考えていきます。それを通して専門家と一般の方々の間のコミュニケーション不全を少しでも改善したいと思っています。お気軽にご参加ください。
2012年度後期のサイエンスカフェは終了しました
最新のサイエンスカフェはこちらをご覧ください
| 開催場所: | 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館3階セミナー室 |
|---|
| 開催時間: | 毎回午後2:00〜3:30まで(午後5:00閉館) |
|---|
| 定 員: | 各回とも20〜30名程度 |
|---|
| 参加費用: | 飲み物代(200円)が必要 |
|---|
| 共 催: | 豊中市立中央公民館 |
|---|
| 協 力: | 大阪大学21世紀懐徳堂・とよなかサイエンスネット実行委員会 |
|---|
No. 100:漢方ことはじめ
コーディネーター:東 由子(薬学研究科)
実施日:2012年12月22日(土)/ 対象:高校生以上 終了しました
現在はエキス製剤として顆粒や細粒で処方される漢方薬ですが、もともとは複数の刻み生薬を混合したものを煎じて飲む煎じ薬です。漢方薬とは何なのか、西洋薬とどう違うのか、漢方薬に配合されている生薬を実際に触っていただきながら、漢方薬の基礎について楽しく学んでいただけたらと思います。
No. 101:誰もが使える未来のコンピュータ
コーディネーター:伊藤 雄一(クリエイティブユニット)
実施日:2013年1月26日(土)/ 対象:小学校高学年以上が望ましい 終了しました
コンピュータを使うのにマウスやキーボードはもう古い。じゃあ未来のコンピュータはどのように使われるのだろうか?iPadやiPhoneなどのようにタッチパネルを使ったものになるのか、それとも…コンピュータを使うためのデバイスに焦点を当て、その最新の研究を紹介し解説します。そして、もっともっとコンピュータを便利に使うにはどうしたらよいか、その未来を一緒に考えてみましょう。
No. 102:細菌の中ではたらく超精密機械
コーディネーター:今田 勝巳(理学研究科)
実施日:2013年2月2日(土)/ 対象:中学生以上 終了しました
ときに深刻な食中毒を引き起こす大腸菌やサルモネラ菌などの細菌。その多くが泳ぐことを知っていますか?しかも単に泳ぐだけでなく、栄養の周りに集まったり、毒を感知して逃げたりします。このとき働くのが、直径2万分の1ミリに満たないタンパク質でできた小さなモーター。まるで「機械」のような形のこのモーターは毎分1万回転以上のスピードで回ります。バイキンといえども侮るなかれ。細菌の持つ驚くほど精密でふしぎな「機械」のしくみを紹介します。
No. 103:ホタルの光のひみつ
コーディネーター:豊田 二郎(総合学術博物館)
実施日:2013年2月9日(土)/ 対象:制限無し
終了しました
ホタルを素手でとったことがありますか?熱かったでしょうか?いまでは、アニメ映画「火垂るの墓」でしかホタルを知らない人も多いかもしれません。ホタルが光るしくみとまったく同じことを試験管の中で行い、電灯とは違う光(化学発光)の性質と酵素反応について、参加者全員に体験していただきます。
No. 104:近代の芸能
コーディネーター:横田 洋(総合学術博物館)
実施日:2013年2月16日(土)/ 対象:中学生以上 終了しました
明治時代「芝居」といえば、それはほぼ歌舞伎のことを指していました。しかし、昭和になるころには、さまざなな新しい芸能が生まれ、「芝居」という言葉の指す対象も大きく変化しました。近代には様々な芸能が生まれると同時に、それ以前から存在した歌舞伎などの芸能も大きく変化していきました。近代の流れの中で歌舞伎のような芸能がどのように変化したのか。どのようにして新たな芸能が生み出されたのか。近代の芸能の問題点について考えます。
No. 105:頼りになる薬剤師:「賢い薬の使い方」教えます
コーディネーター:須磨 一夫(薬学研究科)
実施日:2013年3月16日(土)/ 対象:制限なし 終了しました
お薬とは、一体、何なのでしょうか?口から飲んだり食べたりするのは食べ物も同じです。食品とお薬の違いや、それぞれの役目をいっしょに考えてみましょう。現在、お薬は用途によって多くの種類が有ります。医療用や一般用にも別れています。どれぐらいの数があると思いますか?身近な疑問に、頼りになる薬剤師がお答えします。さらに現代社会で活躍する薬剤師の多様な仕事をご紹介したいと思います。
No. 106:生活と元素
コーディネーター:桜井 弘(京都薬科大学名誉教授)
鈴木 晋一郎(大阪大学名誉教授・理学研究科)
実施日:2013年3月23日(土)/ 対象:中学生以上 終了しました
この2年ほど、レアアース元素の国際的問題、原子力発電所事故による放射性元素の環境への放出と健康への影響、あるいは新元素の名前が二つ決まったなどが報道され、人々の元素への関心は急速に高くなっています。そこで、元素とは一体なにか?を元素周期表との関係で考え、さらに体の中の元素にはどのようなものがあり、それぞれはどのように働いているか? について易しく紹介します。
No. 107:くすりの不思議:くすりができるまで
コーディネーター:森崎 智子(薬学研究科)
実施日:2013年3月30日(土)/ 対象:制限なし 終了しました
「一つの新しい薬が見つかってから患者さんの手元へ届くまでに、どんなプロセスがあるの?」「薬には錠剤やカプセル、注射剤等、様々な形があるのはなぜ?」「副作用のない薬はあるの?」「薬によって服用タイミングが違うのはなぜ?」「病院でもらって余った薬はまた使ってもいい?」等、薬に関する疑問を分かりやすくご紹介します。身近にあるのに、実はよく知らない薬のことを一緒に謎解いてみませんか?
|