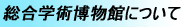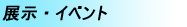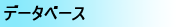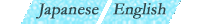サイエンスカフェ@待兼山
大阪大学総合学術博物館で、サイエンスカフェを楽しみませんか。コーヒーを片手にゆったりとした雰囲気で、「科学する」とはどういうことか、研究者とともに考えていきます。それを通して専門家と一般の方々の間のコミュニケーション不全を少しでも改善したいと思っています。お気軽にご参加ください。
| 開催場所: | 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館3階セミナー室 |
|---|
| 開催時間: | 毎回午後2:00〜3:30まで(午後5:00閉館) |
|---|
| 定 員: | 各回とも20〜30名程度 |
|---|
| 参加費用: | 飲み物代(200円)が必要 |
|---|
| 共 催: | 豊中市立中央公民館 |
|---|
| 協 力: | 大阪大学21世紀懐徳堂・とよなかサイエンスネット実行委員会 |
|---|
2012年度前期のサイエンスカフェは既に終了しました
最新のサイエンスカフェはこちらをご覧ください
No. 89:『論語』を読む
コーディネーター:湯淺 邦弘(文学研究科)
実施日:2012年7月21日(土)/ 対象:制限なし 終了しました
『論語』の研究は近年大きな転換期を迎えています。竹簡資料が大量に古墓から発見され、成立や伝播について新たな解明が進んでいるのです。そこでまず、竹簡とは何か、またどうしてそれが二千年以上前のものと科学的に鑑定できるのか、について解説してみましょう。そして、著名な『論語』の言葉を取り上げながら、孔子やその弟子たちが目指したものは何だったのか、一緒に考えてみましょう。
No. 90:最新の航空機技術
コーディネーター:辻本 良信(基礎工学研究科)・宮本 洋(JAL)
実施日:2012年7月28日(土)/ 対象:高校生以上 終了しました
JALにおいて長年航空機整備に携わった経験をもとに、主力航空機ボーイング777や最近導入が進んでいる787を例に、最新の航空技術に関し解説する。具体的には騒音・燃費向上を目指したエンジン技術、軽量化を目指した新素材の適用、軽量化・燃費向上を目指した制御技術などについて解説する。
No. 91:古い時代の英語の文字について ―― 古英語を中心に
コーディネーター:加藤 正治(文学研究科)
実施日:2012年8月4日(土)/ 対象:高校生以上 終了しました
どの言語も時代とともに変化しますが、文字も同じように変化します。英語の文字も現代と古代ではかなり異なっています。今回は古英語(1100年までの英語)の文字、字体などに関するエピソードを中心にお話しいたします。
No. 92:はじめての漢方
コーディネーター:島田 佳代子(薬学研究科)
実施日:2012年8月11日(土)
対象:中学生以上、学生・家族連れ歓迎 終了しました
最近テレビでもよく耳にする『漢方』。どんなかたち?どんな味?どんなにおい?どんなふうに使われているの?お医者さんでもらうカプセルや錠剤とは何が違うの?――など、様々な疑問をお持ちかと思います。夏休みを利用して、漢方の世界を少しだけ覗いてみませんか。見て、触って、味わって、五感をフルに使って漢方の世界を体験しましょう。
No. 93:「音声」「音声信号処理」を身近に感じよう!
コーディネーター:川村 新・早坂 昇(基礎工学研究科)
実施日:2012年8月18日(土)/ 対象:制限なし 終了しました
皆さん,人と会話するときに使っている「音声」についてもっと詳しく学んでみませんか?その「音声」を使いやすく処理する「音声信号処理」がスマートフォンなど身近な製品に入っているのを知っていますか?実は「音声」にはその他の音とは違ういろんな特徴を持っています.その特徴をうまく使った処理の中で,雑音に埋もれた「音声」の「復元」,2人の会話が混ざった「音声」の「分離」,話した「音声」の「認識」について紹介し,実演,体験から「音声信号処理」を身近に感じてもらいます.
No. 94:日本中世ぽちたま物語
コーディネーター:芳澤 元(文学研究科)
実施日:2012年8月25日(土)/ 対象:制限なし 終了しました
現代社会は空前のペット・ブームですが、人類はむかしから、多くの動物たちと長い歳月を共に生きてきました。近年では日本史学の中でも、人と動物の関係について、さまざまな事実や問題が解明されています。そうした成果に学びながら、われわれにも身近な存在である犬や猫との関係をめぐって、過去の人々が築いてきた社会生活について、ご一緒に考えてみたいと思います。
No. 95:放射能とは―身の回りの放射能を調べてみよう―
コーディネーター:篠原 厚(理学研究科)
実施日:2012年9月1日(土)
対象:中学生程度以上、親子連れも可 終了しました
放射能、放射線とは何かを、できるだけ簡単に基本的概念を説明する。また、グループ実験として身の回りの放射線やデモ用の試料などを、実際にサーベイメータを使って測ってみることで、より理解を深めたい。また、時間があれば放射線の人体への影響や社会との関わりについて話し合う。
No. 96:東日本大震災で起こった巨大津波の原因を探る
コーディネーター:廣野 哲朗(理学研究科)
実施日:2012年9月8日(土)/ 対象:中学生以上 終了しました
2011年東日本大震災では、10mを遙かに超える巨大津波が発生しました。これほどまでに大きな津波の発生には、海底の断層のズレが関係しているでしょう。では,このズレはなぜ生じたのでしょうか。この原因を解くカギは「摩擦係数」です。地震と津波という現象を物理と化学という視点で解説していきます。
No. 97:分子の右手と左手を作り分ける
コーディネーター:真島 和志(基礎工学研究科)
実施日:2012年9月29日(土)/ 対象:高校生以上 終了しました
分子の炭素にある対称性を紹介し、これを作り分けることが薬を作る上で大事であることを説明します。
No. 98:平清盛とその時代
コーディネーター:川合 康(文学研究科)
実施日:2012年10月6日(土)/ 対象:中学生以上 終了しました
鎌倉幕府成立後に成立した『平家物語』は、「おごれる人」の代表的人物として平清盛をとりあげ、「盛者必衰のことはり」の観点から平氏一門の滅亡を必然視しています。しかし、はたしてそれは史実だったのでしょうか。貴族の日記など、同時代の人々が書き残した一次史料と、歴史学の最新成果に基づ いて、平清盛の実像と当時の武士社会の特質に迫りたいと思います。
No. 99:女性アーティストの作品から見える「ニッポン」
コーディネーター:北原 恵(文学研究科)
実施日:2012年10月13日(土)/ 対象:中学生以上 終了しました
あなたは、どんなアーティストが好きでしょうか? 今回のカフェは、現在活躍している女性アーティストの作品をスライドで紹介しながら、そこから見える「ニッポン」の姿をいっしょに考えます。彼女たちは自らの生や社会の問題をどのように表現しているのか、ジェンダーの視点から検討することによって、どんな「ニッポン」が見えてくるでしょうか。難解だと言われる現代美術も楽しく身近なものに感じられるようになると思います。
|