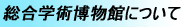  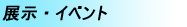 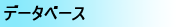  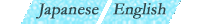 |
大阪大学総合学術博物館 第12回企画展「線の表現力」アートの諸形態、須田国太郎《能・狂言デッサン》から広がって10:30〜17:00 入場無料 日祝、12月29日[水]〜 1月 3日[月]は休館 ただし11月 7日[日]は開館 会 場:大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館 主 催:大阪大学総合学術博物館・大阪大学附属図書館 共 催:大阪大学大学院文学研究科 特別協力:芦屋市立美術博物館 協 力:大阪大学21世紀懐徳堂 開催趣旨 原始の岩窟壁画の時代から、人類は“線”を刻みつけることでコミュニケーションをしてきました。組みあわされた複数の“線”は、言葉を伝える文字となる一方、世界を写しとり、それを表現する絵画へと発展します。中国や日本では、絵画の基本的な要素である「画之六法」の二番目に「骨法用筆」があげられるなど、“線”の存在が重視されます。また、西洋の絵画でも“線”の存在がいかに重要であるかは言うまでもありません。さらに“線”による表現は、現代アートの世界でも多種多様な試みがなされてきています。 この展覧会では、大阪大学附属図書館に寄贈された、日本近代を代表する洋画家・須田国太郎(1891−1961)の《能・狂言デッサン》を中心として、日本の近現代美術における“線”による表現をごらんいただきます。モノの形象を画面に再現する写実的な“線”、それ自体の美しさを主張する“線”、日本画と洋画の“線”の違いなどを紹介します。そして須田国太郎が終生、熱中した能や狂言の舞台スケッチを公開し、写実的でありながらも、演者の動きとともに “線”が加速し、運動を追跡する素描へと変容していくことを示します。最後に、モノの再現を解き放たれ、運動体と化した“線”が、抽象絵画もふくめた新しいアートの表現へと進んでいくことを示します。 展示構成 第1章 “線”は自分の歌を歌い出す─具象化への意志と美しき“線”─ 第2章 運動の軌跡をえがきとめる─須田国太郎《能・狂言デッサン》─ 第3章 “線”は別の歌を歌い出す─抽象化への疾駆、さらに新しい表現へ─ 主な作家 須田国太郎、藤田嗣治、村上華岳、松本竣介、吉原治良、松谷武判、三上誠、佐藤忠良、中山忠彦、中村貞夫、濱田弘明 ほか 展示作品例
ワークショップ 11月6日(土)13:30〜15:00 中村貞夫(画家・宝塚大学講師)「描線を楽しもう―1本の線で描く―」 ※ピカソが得意にした一筆描きの素描をみんなで楽しみましょう。あなたの描いた“線”が会期中、1階ロビーのインスタレーションを飾ります。画用紙、鉛筆は当館で用意しますが、その他、スケッチブック、筆、ペンなど、ご持参歓迎です。 定員40名(先着順) ミュージアムレクチャー 11月 7日(日)13:30〜15:00 【第27回】中村貞夫(画家・宝塚大学講師) 「線描の軌跡」 11月27日(土)13:30〜15:00 【第28回】上野正章(京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター共同研究員) 「愚直な音楽ージョンケージによる図形楽譜の試みー」 12月 4日(土)13:30〜15:00/15:15〜16:30 【第29回】天野文雄(大阪大学名誉教授) 「能と絵の出会いー須田国太郎 能・狂言デッサン再考ー」 【第30回】須田寛(JR東海相談役) 「〈能〉と父・須田国太郎」 ※天野・須田両氏による対談あり 12月11日(土)13:30〜15:00 【第31回】加藤瑞穂(芦屋市立美術博物館主任学芸員) 「行為の痕跡:1950年代〈具体〉作品の線」 3階セミナー室にて開催。いずれも聴講自由、30分前より受付開始。定員60名。 パンフレット (pdf A4両面 1.6MB)
|





