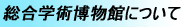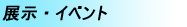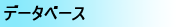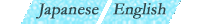総合学術博物館第2回企画展出展案内
ごあいさつ
大阪大学に総合学術博物館が設立されて1年が経過し、徐々にではありますが態勢を整えつつあります。これも学内の皆様の熱烈なご支援の賜物と感謝しております。昨年は10月12日から同20日まで、総合学術博物館の設立を記念して、「いま阪大で何が?―人間・地球・物質」というタイトルのもとに、大阪大学の教育研究の現状を一般の方々に紹介する観覧者参加型の展示会を、大阪歴史博物館とNHK大阪放送局が共同で利用しているアトリウムで開催しました。学内から募集した20チームのブースを配置し、説明パネル、簡単な演示実験、口頭説明により、最近の研究成果を紹介し、9日間で高齢の方から小学生まで約14,000名の観覧者があり、「難しそうなテーマも熱心に説明してもらったのでわかりやすかったし、阪大の研究を身近に感じた」という声が多く寄せられました。ただし昨年は実験をともなう展示を主眼としたために、理科系偏重であるとのご批判もいただきました。そこで本年の第2回企画展は、文科系にも出展しやすいよう改めましたので、大学の「社会貢献」の一環として、あらゆる分野の教職員や学生の皆様の積極的なご応募をお願い申し上げます。
平成15年4月4日
大阪大学総合学術博物館
館長 肥塚 隆
- 名 称
大阪大学総合学術博物館第2回企画展
メインタイトル「調和と共生」展(仮称)
キーワード 交流、接触、協調、共生、融合、境界、インターフェイス、人間と自然、異文化交流、異なるシステムの調整、リストラ、リサイクル、大学改革、文化財や遺跡保存、循環、グリーンケミストリー、エコロジー、地球環境、自然との共生、寄生虫と宿主、共生思想、ユビキタス社会、バリアフリー、地域紛争解決、文科と理科、東洋と西洋、その他。
21世紀初頭のこの混沌とした現在の全人類の最大の課題である「調和と共生」から連想されるキーワードを並べてみました。これらに関連する幅広い展示を募集します。なお、メインタイトルは、出展企画が揃った段階で決定します。
- 開催形態
主催 大阪大学総合学術博物館
共催 大阪歴史博物館・NHK大阪放送局(予定)
後援 未定
- 会期と会場
会期 平成15年10月8日(水)-10月13日(月)(予定) 6日間。ただし、前後各1日を準備と撤収にあてる。
会場 大阪歴史博物館・NHK大阪放送局アトリウム
- 趣 旨
メインテーマに合致する大阪大学の教育研究の現状を展示などによって公開するとともに、市民の知的好奇心を喚起する。museumの語源のmouseion(総合的な学術研究の殿堂)の意義に立ち返り、阪大の「教育研究の見本市」を目指す。ことに阪大の教育研究が懐徳堂、適塾の両学問所の伝統を継承し、「地域に生き世界に伸びる」ことをモットーとしている現状と未来への展望とを紹介し、あわせて科学することの楽しさ、学問することの面白さを伝えることを目的とし、「愛される阪大」作りの一助とする。
- 展示方法
展示方法は、以下の(1)-(3)のいずれかとしてください。
(1)小型機器による演示実験と各種映像やポスターによる展示と説明。標本資料や機器などの実物を展示してもよいが、原則として観覧者が手で触れてもかまわないものに限ります。先端的な研究であっても原理に立ち戻った説明をしてください。
(2)観覧者みずからが体験する、手で触れる、耳で聞くことができる展示で、インターラクティヴな提示方法が望まれます。
・標本資料や写真パネルなどの展示。
(3)ミニレクチャー(演示実験に関する講演やメインテーマに関わる独立した講演。1回30分程度で1日に5件程度)。
・各ブースにおいて期間中は必ず最低1人の説明員をおき、土曜・日曜・祝日には複数の説明員、演示実験担当者を配置してください。
- 対象
研究者を対象とするのではなく、社会人、大学生、高校生、中学生、小学生を対象とします。社会人から小学生まであらゆる年齢層を対象とするか、特定の年齢層を対象とするかは、展示発表者の自由です。
したがって一般の人々が興味をもちそうなテーマを選び、パネルの説明文は短くかつ平易を旨としてください。
- 展示発表者
原則として、展示発表者は阪大の教職員と学生より公募します。5の(1)と(2)は、個人でもグループでもかまいません、両方で20チーム程度の出展を考えております。(3)は個人で20-30人程度の予定です。
- 出展の申込方法
別紙の「総合学術博物館第2回企画展出展申込書 」の体裁に従い、の体裁に従い、5月30日(金)までに大阪大学総合学術博物館(〒560-8532豊中市待兼山町1-5)に送付するか、e-mail (kikaku @ museum.osaka-u.ac.jp)で「Word」の添付ファイルとしてお送りください。「申込書」の「必要電力」の項以下は、申込段階では概数で結構です。またご質問その他のお問い合わせは、e-mail (文科系の出展の場合は肥塚隆koezuka @ museum.osaka-u.ac.jp、理科系の出展の場合は江口太郎eguchi @ museum.osaka-u.ac.jp)へお願いします。なおこの出展案内は、http://www.museum.osaka-u.ac.jp/ でもご覧いただけます。
- 展示発表者の決定
6月中旬までに総合学術博物館企画委員会で、展示発表者を決定します。
- 展示形態
・小間の基本形態(パッケージブース)
1小間:間口1.8 m、奥行0.9 m、高さ2.4 m、後壁、展示台(間仕切りは付けません)。
原則として1チーム1小間。
・標本資料をガラスケースに展示する場合や、写真展示の壁面の仕様は、出展者と相談の上、決定します。
・電気の供給と情報コンセント
取り出しの配線等は基本的に主催者が行います。
・給排水と火気
水道設備はなし(床が濡れるような展示・演示実験は難しい)。
火気の使用については、消防署よりかなり厳しい制限があります。
・安全への配慮
出展者は観覧者の安全への配慮を徹底してください。
・その他
展示ブース、展示台、展示ケース、展示パネル、電源、監視要員などは、主催者が用意します。
アルバイト補助:1チームあたり5万円程度を予定(検討中)。
ミニレクチャーの講演謝礼
- 宣伝と案内状
阪大公式ホームページ、総合学術博物館ホームページ。
マスコミ、タウン誌に広報し、近隣自治体の教育委員会、大阪府下(あるいは近隣の府県)の高等学校へチラシやポスターを配布する予定です。
- スケジュール
5月30日 募集締切
6月中旬 展示発表者の決定、第2次展示案内の送付
7月下旬 展示発表者のパンフレット原稿締切
8月中旬 ポスター、ちらし、案内状の原稿締切
8月下旬 パンフレットの原稿完成、印刷所へ
9月上旬 ポスター、案内状の発送
10月中旬 開催
|
|