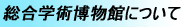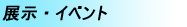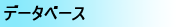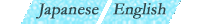2003年9月1日
大阪大学総合学術博物館
大阪大学総合学術博物館第2回展示会(「関西元気文化圏」参加事業)
|
『ジグソーのピースを探して-調和と共生-』
「調和と共生」は「ビールと枝豆」の関係のようなもの…!?
癌治療法最前線からファッション、モードまで、
柔らか頭で“旬の阪大”を体験できるイベント開催!
(開催期間) 2003年10月8日(水)-10月13日(月)
(開催場所) 大阪歴史博物館・NHK大阪放送局アトリウム
|
|---|
|
|---|
大阪大学総合学術博物館(大阪府豊中市)は2003年10月8日(水)-10月13日(月)の6日間、大阪歴史博物館・NHK大阪放送局アトリウムで『ジグソーのピースを探して―調和と共生―』と題し、大阪大学で現在行われている研究の中から“調和と共生”に関連する研究の成果を展示やミニレクチャーで分かりやすく紹介するイベントを開催します。(「関西元気文化圏」参加事業)
当展示会は21世紀初頭の混沌とした現代の課題を解決するためのキーワードである「調和と共生」をテーマに開催します。会場での錯覚体験を通して視覚を担う脳のメカニズムを説く「脳が見る、脳を見る(認知脳科学への招待)」、医学部付属病院で開発が進められている新しい発想の癌治療法「今川義元を射る-癌治療の新しい戦法-WT1を標的とした免疫療法」、近年の混乱のうちに失われたアフガニスタンの文化遺産を紹介する「アフガニスタンの失われた仏たち」や「文化遺産にみる日本の香」をはじめ、理科系、文科系合わせて全22チームが展示、17人がミニレクチャーを行う知の体験イベントです。
<特徴>
(1) 21世紀の重要なキーワードとなる「調和と共生」に関連する最新研究成果の披露
(2) 小・中学生から社会人・高齢者までの幅広い層に分かりやすい解説に挑戦
(3) 展示だけでなく、ミニレクチャーによる講演も実施
<趣旨>
当展示会は次の3つをポイントに、身近で親しみのある開かれた大阪大学を目指して開催します。
(1) 総合学術博物館として、“museum”の語源の“mouseion”(総合的な学術研究の殿堂)の意義に立ち返り、当展示会が大阪大学の「教育研究の見本市」となることを目指します。
(2)大阪大学の教育研究が懐徳堂、適塾の両学問所の伝統を継承し、「地域に生き世界に伸びる」ことをモットーとする現状と未来への展望を紹介します。
(3)来場者の知的好奇心を喚起するとともに、学問の楽しさ、おもしろさに触れていただくことに努めます。
当展示会の開催概要は次の通りです。
『ジグソーのピースを探して―調和と共生―』について
| 【タイトル】 | 大阪大学総合学術博物館第2回展示会 |
|---|
| 『ジグソーのピースを探して―調和と共生―』 |
|---|
| 【開催日時】 | 2003年10月8日(水)-10月13日(月) 10:00-17:00 |
|---|
| 【会 場】 | 大阪歴史博物館・NHK大阪放送局アトリウム |
|---|
| 【料 金】 | 無料 |
|---|
| 【主 催】 | 大阪大学総合学術博物館 |
|---|
| 【共 催】 | 大阪歴史博物館、NHK大阪放送局 |
|---|
| 【概 要】 | 「調和と共生」をテーマに、大阪大学の教職員と学生からの応募による参加 |
|---|
◇展示概要(22チーム)
- 脳が見る、脳を見る─認知脳科学への招待─
(生命機能研究科脳神経工学講座 藤田一郎、田村弘)
黒白の絵なのに色が見える、静止画なのに動いて見える、両目で見えて片目では見えないなど、「ものを見る」脳のメカニズムはどうなっているのか、様々な錯覚体験を通して科学者がそれをどのように調べているのかを紹介します。
- 今川義元を射る─癌治療の新しい戦法─
(医学部附属病院 池亀和博、杉山治夫)
医学部附属病院で現在開発が進められている新しい癌治療法、WT1を標的とした免疫療法を説明するとともに、新しい治療法の開発過程で研究者達がどういう発想でものを考え、悩み、乗り越えようとしているかなど、医師のもう一つの素顔を紹介します。
- サルからヒトへの人間科学─「からだ」と「こころ」の進化─
(人間科学研究科行動生態学講座 熊倉博雄、中道正之、中野良彦)
ヒトの適応の由来をサルに求める研究を、ソフトウェアとしての「行動(こころ)」と「形態(からだ)」の両面から紹介。霊長類の特徴が、ヒトに至っていかに「かたち」を変えたかを示します。
- ニハイチュウとタコ・イカ類との共生
(理学研究科適応生物学講座 古屋秀隆、常木和日子)
タコやイカの腎臓には、体長1mm前後の原始的な動物「ニハイチュウ」が寄生していま す。その日本近海産のニハイチュウは宿主とともに進化してきたと考えられています。生きている状態を顕微鏡で観察し、共生について考える機会を提供します。
- 植物が作り出した物質(くすり)がヒトの病気を治す
(薬学研究科天然物化学分野 小林資正、村上啓寿)
現代医療に用いられる医薬品の多くが薬用植物や微生物の代謝産物から見出された化合物です。有名な薬用植物の写真やそこから見出された薬物の化学構造式を掲示し、カンゾウ、薬用ニンジンほか有名な生薬を展示、刻み生薬をなめて味わえます。
- 生物の共生─マメと根粒菌の助け合い─
(情報科学研究科生物共生情報工学講座 室岡義勝、林誠)
マメは土壌細菌である根粒菌と細胞内共生することでふつうの植物が生育できない荒れた土地でも繁殖し、パイオニア植物の役割を果たします。その共生ぶりを顕微鏡で観察してもらうとともに、共生の有効利用、生物の共生について機構解明の最新研究を紹介します。
- 循環型社会の構築に寄与する光による環境浄化
(接合科学研究所スマートコーティングプロセス学分野 中出且之、大森明)
リサイクルしたペットボトル等の表面に「光触媒」の粉末を溶射すると、環境をきれいにする機能を有するプラスチックが作成できる。表面の性質を変える最新の溶射技術が、循環型社会に寄与できることを紹介します。
- 自然にやさしく、人にやさしい化学の創成
(21世紀COEプログラム「自然共生化学の創成」 原田明、桑畑進、柳田祥三、大垣一成)
21世紀COEプログラム「自然共生化学の創成」は、「自然と人間が共生できる社会の実現」を可能とする化学の創造を目的としています。本展示では「エネルギー」に関する研究をわかりやすく紹介します。
- 最先端ナノテクノロジー材料─機能が調和した材料と人間との共生─
(産業科学研究所セラミック構造材料研究分野 新原晧一、山本泰生、関野徹、楠瀬尚史、中山忠親、林大和)
大阪大学におけるナノ材料研究の歴史から、ごく最近の最先端の研究成果や将来への展開を示すとともに、人間との共生を目指してロボットや楽器、情報機器に応用されつつあるナノ材料を用いた製品等に触れることで、理解を深めていただきます。
- 人工歯根との共生─最小限のインプラントでうまくかむ─
(歯学部附属病院口腔総合診療部 前田芳信、十河基文、山本英貴)
現状では、歯の“インプラント治療”は容易にできる治療とはいえません。その改善のための研究として、インプラントの本数の違いによる、あごの骨が受ける力のシミュレーションと最新の磁石による入れ歯の固定法を紹介します。
- 見て、作って、楽しもう─魅力ある物理実験─
(理学研究科物性物理学講座 藤井研一)
共通教育での物理学実験の紹介。基礎教育科目「物理学実験」説明用ビデオダイジェスト版と実験風景上映。基礎セミナー「先端物理現象」で作成したホログラムと超伝導が体験できます。
- 近代地図作製をめぐる中国と日本─技術移転と秘密測量─
(文学研究科人文地理学講座 小林茂、堤研二、鳴海邦匡、渡辺理絵)
旧日本軍が作製した国外地域の地図「外邦図」の中でも長期間かつ広範囲に行われた中国の作製過程の一部を示すとともに、陸地測量部修技所における中国人留学生の修学関係資料も展示します。
- 埋蔵文化財調査室の活動─埋蔵文化財と現代社会の共生─
(埋蔵文化財調査室/文学研究科考古学講座 寺前直人、福永伸哉)
大阪大学埋蔵文化財調査室は、2001年に大阪市北区中之島の久留米藩大坂蔵屋敷跡を調査しました。今回は、中之島の調査の紹介とその時の都市開発と埋蔵文化財の共生および埋蔵文化財の活用について考えます。
- 大阪近代黎明期の西洋諸科学との交流
(医学研究科社会環境医学講座 多田羅浩三)
明治新政府は大阪に理化学の舎密局と仮病院を設置し、大阪が高等教育を目指す総合大学の様相をもつことになった。大きな影響を残した三人のオランダ教師の講義録などを展示します。
- 近現代大阪経済史─2つのパノラマ─
(経済学研究科歴史分析講座 宮本又郎、澤井実)
大阪の企業家たちは戦間期から戦時期にかけて進行する重化学工業化の動きにどう対応し、アジアとの密接な関係をいかにして拡大したのか。パノラマ写真などを使って、近現代大阪経済史の歩みを紹介します。
- アフガニスタンの失われた仏たち
(総合学術博物館 肥塚隆)
アフガニスタンは「文明の十字路」であり、さまざまな民族が侵入した戦乱の地でもあります。1975年と77年に撮影したバーミヤーンを中心とする遺跡や文化財の写真を展示し、その歴史と文化を紹介します。
- 人と人をむすぶ音楽
(21世紀COEプログラム「インターフェイスの人文学」 山口修)
アジアやオセアニア、そしてヨーロッパの音楽を紹介しつつ、その研究成果が「人と人」のつながりから生まれたことを説きます。一教官の足跡を音、写真、動画のかたちで辿る場を提供します。
- ロースクールの発進─21世紀型法曹の養成をめざして─
(法学研究科国際・比較法講座 中尾敏充)
平成16年4月開設予定の大阪大学大学院高等司法研究科(ロースクール)は、双方向的・対話的な密度の濃い授業や、商都大阪にふさわしくビジネス法を重視した教育を行う計画です。その実現に向けた取り組みを紹介します。
- 大阪大学総合学術博物館を中心とする待兼山ゾーンの将来構想
(工学研究科環境デザイン学講座 鳴海邦碩、藤井豊史)
大阪大学豊中キャンパス内の待兼山は、マチカネワニの化石や古墳群等各種の遺跡の宝庫です。ここに計画中の、周囲の生態系や遺構類、各種学術研究成果を保存展示する博物館と待兼山の環境やイメージを模型やコンピュータ・グラフィックスで紹介します。
- 江戸時代の天体模型図─懐徳堂の知の宇宙─
(文学研究科懐徳堂センター/(財)懐徳堂記念会 湯浅邦弘)
大阪大学の源流「懐徳堂」については近年、懐徳堂文庫約5万点の総合調査が進められています。今回の展示では、パソコン、パネル、レプリカなどの複合展示により懐徳堂の世界が体感できます。
- 出版活動─大阪大学出版会─
(岩谷美也子)
出版会では、大阪大学創立70周年記念出版として刊行した「大阪大学新世紀セミナー」、大学の源流である「適塾」「懐徳堂」関係の概説書などを中心に読書コーナーを設け、出版会の本を実際に手にとって親しんでいただく場を提供します。
- ミニ広報プラザ
(事務局総務部企画広報室)
大阪大学の現状を大学公式ホームページや大学紹介ビデオ、広報誌等の印刷物などで紹介します。また、説明者を配置して“大阪大学”に関するさまざまな質問や問い合わせにも対応します。
◇ミニレクチャー概要(17人)
- ミクロな穴で悪臭を捕らえる
(総合学術博物館 上田貴洋)
悪臭を除去する脱臭剤。目に見えない小さな孔が、臭いの成分(分子)を捕まえる様子(メカニズム)を説明します。
- 磁石の力で人間をみるMRIのお話
(総合学術博物館 江口太郎)
病院の画像診断によく使われるようになったMRIについて、その原理をやさしく解説します。
- ナGノなぞなぞナノだ!
(産業科学研究所 山本泰生)
目に見えない小さなナノ粒子でも、その働きは目に見える。そのナノ粒子が人の暮らしに役立つことを解説します。
- WT1を標的とした癌免疫療法
(医学部附属病院 池亀和博)
WT1という蛋白は癌細胞にたくさんでています。これを標的として免疫の力で癌をやっつけようという試みを解説します。
- 最も単純な多細胞動物ニハイチュウ
(理学研究科 常木和日子)
タコやイカの腎臓内に住むニハイチュウについて、その動物としての特徴や宿主との関係について紹介します。
- アフガニスタンの失われた仏たち
(総合学術博物館 肥塚隆)
近年の混乱のうちに失われたアフガニスタンの文化遺産を、1970年代に撮影したスライドで紹介、解説します。
- 文化財に見る日本の香
(総合学術博物館 米田該典)
日本の伝統文化の香と香遊びの姿や歩みを各地に伝わる文化財の中からたどる研究を報告します。
- モードの終わり?-ファッションの現在を考える-
(文学研究科 鷲田清一)
世紀末、モード(流行)がもはや人を誘惑しなくなったようにみえます。「服もやがてモードでなくなるのだろうか?」。このことについて論じてみます。
- サルからヒトへの人間科学 ─ニホンザルの行動と社会を探る─
(人間科学研究科 中道正之)
野生ニホンザルの母子の結びつきや集団のメンバーの密接な関わり。ヒトに近縁のサルの世界に案内します。
- 脳が見る、脳を見る ─認知脳科学への招待─
(生命機能研究科 藤田一郎)
様々な錯覚をその場で体験し、「ものを見る」背景に深淵な科学的問題が潜んでいることを知る。
- 自然にやさしく、人にやさしい化学の創成
(21世紀COEプログラム「自然共生化学の創成」 原田明)
自然と人間と共に生きてゆく方法を探る。大阪大学化学系の21世紀COEプログラムについて解説します。
- 暗号とインターネット
(総合学術博物館 豊田二郎)
暗号というとスパイ映画のようですが、強力な暗号があるからこそインターネットで安全に買い物ができます。その仕組みを解説します。
- ネットワーク共生環境におけるヒューマンインターフェース技術
(情報科学研究科 岸野文郎)
人、もの、環境がコンピュータ,センサ,ネットワークで結合された共生環境を使い易くする技術を紹介します。
- 江戸時代の天体模型図─懐徳堂の知の宇宙─
(文学研究科 湯浅邦弘)
大阪大学の源流「懐徳堂」─その豊かな知的世界の一端を、200年前の天体模型を使って解説します。
- 近代地図作製をめぐる中国と日本─技術移転と秘密測量─
(文学研究科 小林茂)
陸軍陸地測量部修技所の中国人留学生の記念写真を中心に、近代地図作製をめぐる中国と日本の関係を考えます。
- サンタクロースの島の教会
(総合学術博物館 大橋哲郎)
トルコ地中海沿岸のゲミレル島の発掘現場とそこで発見されたビザンチン・モザイクを紹介します。
- 人と人をむすぶ音楽、そしてその記録
(21世紀COEプログラム「インターフェイスの人文学」 山口修)
諸民族の音楽を視聴覚機器で記録することの意義と問題点をミクロネシア、ベトナム等での経験から解説します。
大阪大学総合学術博物館について
| 【施設名】 |
大阪大学総合学術博物館 |
| 【所在地】 |
豊中市待兼山町1-16 |
| 【設立】 |
2002年4月1日 |
| 【館長】 |
肥塚 隆 |
| 【人員】専任教官 |
6人 |
| 兼任教官 |
36人(全研究科、学部、研究所、センター) |
| 事務官 |
1人 ※ほか事務補佐員2人、技術補佐員1人 |
| 【活動趣旨】 |
懐徳堂と適塾から多くの文化財を継承するとともに、1931年の創立以来の教育研究の成果として収集保存してきました多数の学術標本を研究室や部局の枠を越えて保存・活用します。 |
| 【施設概要】 |
(1)学術標本を可能な限り変質や劣化を防いで保存します。
(2)学内の各所に分散して所蔵されている標本のもつ情報を一元的に管
理し、学内の教職員や学生はもとより、学外の方々も容易にその情報を利用できるシステムを整備し
ます。
(3)特定の目的をもって収集された標本を異なる分野の研究者に提供す
るために、共同研究推進のコーディネーターとしての役割を担います。
(4) 大学における教養教育のみならず、初等・中等教育やそこにおけ>る総合学習、一般社会人の生涯学習に標本を活用する方法の開発を行います。 |
「関西元気文化圏」について
河合隼雄文化庁長官が提唱する「日本の社会を文化で元気にしよう」の取り組みの一環として、文化庁と関西の関係団体との連携により、平成15年夏から継続的に京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県にまたがる関西地域において「関西元気文化圏-『文化』で関西から元気になろう-」を推進していく活動です。
この「関西元気文化圏」では、関西地域の経済団体、関係事業者、報道機関、行政機関等の積極的な協力体制の枠組みの下、文化団体や企業が行う文化関連事業、自治体の関係事業、文化庁の関係事業など多様な文化活動を展開することにより、文化圏の一体化・活性化を一層推進し、関西から日本の文化が力強く発信されることをねらいとしています。
「文化力」ロゴマーク
大阪大学総合学術博物館
資料先端研究系教授 江口 太郎
〒560-0043 豊中市待兼山町1-16
TEL:06-6850-5778(ダイヤルイン) FAX:06-6850-5785
|