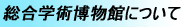  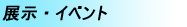 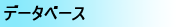  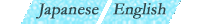 |
サイエンスカフェ@待兼山(2009年前期)"土曜の午後はミュージアム"阪大博物館のサイエンスカフェも2年目を迎えました。昨年は初めての経験で手探りで始めましたが、おかげさまで大好評でした。コーヒーを片手にクッキーをつまみながら「科学する」とはどういうことかを、研究者とともに考えていきます。そのことを通して専門家と一般の方々の間のコミュニケーション不全を少しでも改善したいと願っています。 大阪大学の総合学術博物館、理学研究科、基礎工学研究科、薬学研究科、文学研究科、大学教育実践センターの教員や院生有志がコーディネーターを務める予定です。 <
No. 28:味の話 コーディネーター:小倉 明彦 (大学院理学研究科) 2009年7月11日 対象:小学生〜一般 (親子連れ歓迎) 内容: 同じコーヒーを飲んで、私の感じている味と、あなたの感じている味は同じでしょうか? そもそも食物の味って何でしょうか? 味を舌だけで味わっていると思ったら大間違い。簡単な実験をしながら、考えてみましょう。 No. 29:ロボットと仲良くしよう コーディネーター:新井 健生 (大学院基礎工学研究科) 2009年7月25日 対象:中学生以上が望ましい 内容: 6本足の昆虫型ロボットや人型ロボットの動作の実演を行います.触ったり,操縦したりして,ロボットの仕組みや働きを理解します.そして,このようなロボットたちが世の中でどのように役に立つかを一緒に考えてみたいと思います. No. 30:宇宙から極微の世界まで(II)−自然界に於ける保存則ー コーディネーター:藤田 佳孝 (大学院理学研究科) 2009年8月8日 対象:高校生以上 内容: 宇宙から極微の世界まで・・・現実に目の前に広がる自然からはじめ、人類が認識しているより大きな世界:星、銀河、宇宙、またより小さな世界:分子、原子、原子核、クオークと、我々は自然界に対する認識を広めつつあります。しかし見た目の多様さとは異なり、自然界は驚くほど単純で基本的な要素の組み合わせで出来ているようです。たとえば、おおもとの力(相互作用)は、重力、電気磁気の力、弱い相互作用、強い相互作用の四つしかありません。また大宇宙から原子核、クオークの極微の世界まで、エネルギー、運動量、角運動量、電荷などの「物理量」が保存されているようです。そのような力や保存則について、しばし思いを馳せてみましょう。 No. 31:歴史学研究のフロンティア コーディネーター:廣川 和花 (総合学術博物館) 2009年8月22日 対象:中学生以上 内容: 大学の歴史学専攻では、環境史や科学技術史など、高校までには習わない分野の研究が進められています。「疾病史」もそうした文理融合的な新しい研究分野の一つです。病気や医学は自然と人間の相互作用の歴史であり、現在の医療をとりまく環境はその重層のうえに成り立っています。新型インフルエンザなど、現代の病気や医療をとらえるリテラシーを身につけることがこのカフェの目標です。 No. 32:熱と温度の話 コーディネーター:上田貴洋 (総合学術博物館) 2009年8月29日 対象:小学5、6年生以上 内容: 我々が、熱く感じたり、冷たく感じたりするのは、温度が変わるからです。これは、物質のもつ熱エネルギーと密接に関係しています。では、温度が変わるって、どういうことでしょう。我々の身の回りの現象を例にとって、温度と熱の関係について考えて見たいと思います。 No. (33):炭素をもっと知ってみよう コーディネーター:蔵田 浩之 (大学院理学研究科) 2009年9月5日 対象:中学生以上 内容: 炭素は,私たちにとって最も身近であると共に,最も重要な元素といっていいでしょう.鉛筆の芯が炭素ならば,ダイヤモンドも炭素.また,私たちの身体は炭素なしでは成り立ちません.本カフェでは池田炭から機能性有機化合物,そしてカーボンナノチューブに至るまで,炭素にまつわる様々な話を紹介し,この多彩(多才)な元素に対する認識を新たにしてもらえれば,と思っています. No. (34):植物の見分け方の話 コーディネーター:道下 雄大 (薬学研究科) 2009年9月19日 対象:高校生以上 内容: 植物を見分けるためには、様々なコツがあり、書物では得られない知識・経験を積み重ねる必要があります。名前を知りたい植物(カフェを汚さないもの)があれば各自持参し、五感を使いながらコツを身につけましょう。そもそも、植物を見分けるとはどういうことなのでしょうか? No. (35):ゴムはどうして伸びるの?−ものの性質のなぜ?なに?− コーディネーター:佐藤 尚弘 (大学院理学研究科) 2009年10月10日 対象:制限なし 内容: ゴムはどうして伸びるの?紙おむつはどうして水をそんなに吸収するの?ボールはど うして弾むの?電気を通すものってどんなもの?ろうそくはどうして燃えるの?スケートはなぜ滑るの?日ごろ何の気なしに使っている身近なものの様々な性質を見直 してみましょう。 No. 36:身の周りのもののデザイン コーディネーター:中村 征樹 (大学教育実践センター) 2009年10月17日 対象:中学生以上 申込期間を10月15日(木)まで延長いたします。なお、延長期間中はWebからのお申込のみとさせていただきます。 内容: 世の中を見渡すと,私たちの身の回りは人工物にあふれています。それらの人工物は,一見,哲学や思想とは無縁なように見えます。しかし,そのような人工物にこそ,思想や哲学,政治,社会関係が,具体的な「かたち」をもって埋め込まれているという考え方が,近年,注目されるようになってきました。当日は,参加者のみなさんと,身の周りのもののデザインをとおして,技術と社会の関係について考えてみたいと思います。 No. (37):かえるの子はかえる −遺伝子の正体、DNAとは− コーディネーター:岩井 成憲・山元 淳平 (大学院基礎工学研究科) 2009年10月31日 対象:高校生以上 内容: 『鳶が鷹を産む』というのはたとえの一つであり、言葉どおりのことは起こりえません。あくまで『かえるの子はかえる』、『子は親に似る』です。遺伝子やDNAって何? その構造や機能について、化学的見地からお話ししたいと思います。 ( )つきのカフェ番号は豊中市との共催です。 |

