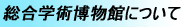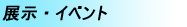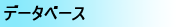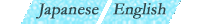サイエンスカフェ@待兼山
2010年度後期のサイエンスカフェは終了しました
大阪大学総合学術博物館で、サイエンスカフェを楽しみませんか。コーヒーを片手にゆったりとした雰囲気で、「科学する」とはどういうことか、研究者とともに考えていきます。それを通して専門家と一般の方々の間のコミュニケーション不全を少しでも改善したい―。3年目に入り、ますますご好評をいただいています。お気軽にご参加ください。
| 開催場所: | 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館3階セミナー室 |
|---|
| 開催時間: | 毎回午後2:00〜3:30まで(午後5:00閉館) |
|---|
| 定 員: | 各回とも30名程度 |
|---|
| 参加費用: | 飲み物代(200円)が必要 |
|---|
| 申込方法: | Webフォーム、あるいは往復はがき
(カフェ1タイトル、住所、氏名、電話番号、年齢を明記。ご家族でお申込の場合、同伴者のお名前、年齢をご記入ください)を下記宛送付。
〒560-0043 豊中市待兼山町1-16 大阪大学総合学術博物館
http://www.museum.osaka-u.ac.jp/ |
|---|
| 申込期間: | 各カフェのタイトルごとにご確認願います(〆切日必着)
応募多数の場合、原則として参加者を抽選で決定します。
当選者には、メールもしくは葉書でお知らせします。 |
|---|
| 協 力: | 豊中市教育委員会・大阪大学21世紀懐徳堂 |
|---|
No. 56:分子の動きを追いかける
コーディネーター:宮久保 圭祐 (総合学術博物館)
実施日:2011年1月8日(土)に終了しました
対象:中学生以上
身の回りのいろいろな物質は分子が集まってできていると学校では教わりますが、それを実感することはあるでしょうか?分子はただ集まっているだけでなく、その中で動くことによっていろいろな現象が起こります。分子の動きはどのようなものなのか、それをどのように調べるのか紹介します。
No. 57:放射線とのつきあいかたーその効用とリスクー
コーディネーター:松多 健策 (理学研究科)
実施日:2011年1月15日(土)に終了しました
対象:中学生以上、親子連れ歓迎
身の回りの自然界には、結構いろんな放射線が飛び交っているって知ってましたか?原子力や星のエネルギーの源であり、原子核の研究は言うに及ばず、医療分野でも、なくてはならない放射線技術。放射線はどんな風に役立っているのでしょうか?危なくないんでしょうか?放射能は地震を起こす?大気の成分に、太古からの放射能の証拠がある?地震予知に使える?このカフェでは放射線を実際に目で見て、放射線とのつきあい方を考えてみましょう。
No. 58:高速道路の渋滞はなぜ起こる−渋滞発生の物理−
コーディネーター:湯川 諭 (理学研究科)
実施日:2011年1月22日(土)に終了しました。
対象:中学生以上、親子連れ歓迎
行楽シーズンになると、よく高速道路での渋滞がニュースになります。なぜ渋滞が発生するのでしょう。単純に道路を走っている車の数が多いからでしょうか。実は渋滞が発生するということの物理的背景には、「相転移」という現象が関係していることが知られています。車の数が多いことはそんなに重要ではなく、水が氷になる時に見られるような相転移が本質的なのです。ここでは渋滞発生の物理について探っていきましょう。
No. 59:「地域」って何だろう?
コーディネーター:堤 研二 (文学研究科)
実施日:2011年1月29日(土)に終了しました。
対象:中学生以上
「地域」という言葉をよく聞きますが、「地域」って何かとたずねられたら、答えるのが意外とかんたんではないようです。またそういう「地域」のことを、どうやって考えたり、調べたりすればいいのでしょうか?こういう、ゆるやかなテーマについて、いっしょに考えましょう。
No. 60:ギターはいつ「カラフル」になったか
コーディネーター:春木 有亮 (文学研究科)
実施日:2011年2月5日(土)に終了しました。
対象:制限なし
現在、世界で最も人気のある楽器の一つと言ってよいギター。いわゆる「クラシック・ギター」は、19世紀のヨーロッパでほぼ現在のかたちにたどりつき、いわゆる「フォーク・ギター」、「エレキ・ギター」は、20世紀前半にアメリカで生まれました。ヨーロッパのギターとアメリカのギターは、さまざまな点で異なりますが、一目見てわかるのは、アメリカのギターが色とりどりであることです。いつ、なぜ、アメリカのギターには「色」がついたのか。100年前のギターの実物を見ていただきつつ、お話します。
No. 61:漢方ってなあに−漢方・入門の入門−
コーディネーター:島田 佳代子 (薬学研究科)
実施日:2011年2月12日(土)に終了しました。
対象:中学生以上(学生歓迎)
みなさんは漢方に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。苦い?高い?なかなか効かない?−最近注目が高まってきている一方で、漢方の真実の姿はあまり知られていません。クイズや体験を通して様々な誤解を解きながら、漢方の世界に迫ってみましょう。
No. 62:ホタルの光のひみつ
コーディネーター:豊田 二郎 (総合学術博物館)
実施日:2011年2月26日(土)に終了しました。
対象:制限なし
ホタルを素手でとったことがありますか?熱かったでしょうか?いまでは、アニメ映画「火垂るの墓」でしかホタルを知らない人も多いかもしれません。ホタルが光るしくみとまったく同じことを試験管の中で行い、電灯とは違う光(化学発光)の性質と酵素反応について、参加者全員に体験していただきます。
No. 63:花びらの枚数の決まり方を考えよう
コーディネーター:北沢美帆、藤本 仰一 (理学研究科)
実施日:2011年3月12日(土)に終了しました。
対象:制限なし・親子連れ歓迎
人間の指の本数は5本、桜の花びらは5枚と、生き物の多くの形には決まった数があります。また、4つ葉のクローバーは幸せの印と言いますから、決まった数から稀(まれ)にずれることもあります。数を決める仕組み、ずれる仕組みは、最先端の科学でもあまりわかっていません。植物の形を眺めながら、数を決める仕組みをあーだこーだと一緒に考えてみましょう。
花が生まれる時には、花びら同士は押しくらまんじゅうのように、お互いに反発しあうようです。各参加者が1つの花びらとなってもらい、その状況を身をもって実験します(激しい運動ではありません)。反発に応じて、花びらがどう配置され、さらに、花びらの数をも決めることができるでしょうか?
No. 64:映画と演劇の歴史
コーディネーター:横田 洋 (総合学術博物館)
実施日:2011年3月19日(土)に終了しました。
対象:制限なし
私たちは数十年も前の古い映画を鑑賞することがあります。また数百年前に書かれた古い演劇作品が現代でも数多く上演され、それらを観賞することができます。古い作品を娯楽としてあるいは芸術として純粋に鑑賞することは大変有意義でまた私たちの楽しみとするところですが、一方で、作品を歴史的な流れのなかでながめていくと、そこにさらに新たな魅力を発見することもできます。歴史的なものの見方が変化すると、作品の歴史的な意義だけでなく、作品の芸術的な価値自体が大きく捉え直されることもあります。映画と演劇とその歴史について考えてみましょう。
No. 65:里山の植物文化
コーディネーター:道下 雄大 (総合学術博物館)
実施日:2011年3月26日(土)に終了しました。
対象:中学生以上
日本では、植物を利用する様々な文化があります。里山でのフィールドワーク、そして各自の経験を通して、里山の文化や植物の存在意義について考えてみましょう。
|