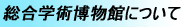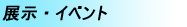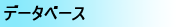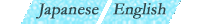サイエンスカフェ@待兼山
大阪大学総合学術博物館で、サイエンスカフェを楽しみませんか。コーヒーを片手にゆったりとした雰囲気で、「科学する」とはどういうことか、研究者とともに考えていきます。それを通して専門家と一般の方々の間のコミュニケーション不全を少しでも改善したいと思っています。お気軽にご参加ください。
| 開催場所: | 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館3階セミナー室 |
|---|
| 開催時間: | 毎回午後2:00〜3:30まで(午後5:00閉館) |
|---|
| 定 員: | 各回とも30名程度 |
|---|
| 参加費用: | 飲み物代(200円)が必要 |
|---|
| 協 催: | とよなかサイエンスネット実行委員会 |
|---|
| 協 力: | 大阪大学21世紀懐徳堂 |
|---|
2011年度前期のカフェは全て終了しました
No. 66:私たちの体の中にある幹細胞
コーディネーター:井上 明男(理学研究科)
実施日:2011年6月18日(土)/ 対象:制限なし
私たちの体の中には幹細胞(組織幹細胞)という何にでもなれる細胞がいて、体が傷ついたときには増殖し分化して傷を治します。この細胞は受精卵にある胚性幹細胞(ES細胞)や人工の胚性幹細胞であるiPS細胞ほど万能性はありません。しかし、ガンにはなりにくくて、病気の治療に使えるのではとたいへん注目されています。この細胞の増殖と分化のしくみはまだ謎のままで、現在多くの研究者によって研究されています。
No. 67:身近なエントロピー
コーディネーター:稲葉 章(理学研究科)
実施日:2011年6月25日(土) / 対象:制限なし
せっかくの熱いコーヒーも,そのうち冷めてしまう.ミルクを加えると,そのうち均一に混ざる.しかし逆に,冷めたコーヒーが突如として沸騰することはないし,いったん混ざったミルクがコーヒーから分離することもない.日常経験するごくありふれた現象は,実は「エネルギー」だけでは説明ができず,「エントロピー」という概念が必要になります.もちろん,エントロピーは実際に測れる量です.そんな熱力学にちょっと触れてみましょう.
No. 68:飛鳥の木簡を読んでみよう
コーディネーター:市 大樹(文学研究科)
実施日:2011年7月2日(土)/ 対象:中学生以上
飛鳥時代(7世紀)は、中国を数百年ぶりに統一した隋・唐帝国の誕生を受け、東アジア世界が激動を迎えた時期にあたります。この時代、日本では律令国家の建設に邁進していきましたが、それは激動の東アジア情勢に対処するための国づくりでした。しかしそれは試行錯誤の繰り返しでもありました。そんな飛鳥時代の木簡を一緒に読んでみませんか。
No. 69:漢方最『後』端!?―『温故知新』古文書から見えること―
コーディネーター:島田佳代子(薬学研究科)
実施日:2011年7月9日(土)/ 対象:制限なし
日々の研究の積み重ねにより、科学分野では次々と新しい論文が発表され、教科書も書き変わっています。しかし、一方の漢方分野では、今でもはるか昔に書かれた『傷寒論』や『金匱要略』などの古典が最も重要な教科書となっています。ここでは『温故知新』『経験知』をキーワードに、江戸時代に書かれた日本の古文書から漢方医学について考えてみましょう。
No. 70:ナノ炭素分子とノーベル賞
コーディネーター:白石 誠司(基礎工学研究科)
実施日:2011年7月16日(土)/ 対象:中学生以上
フラーレン・カーボンナノチューブ・グラフェンなどのナノ炭素分子が今非常に注目されています。少し前まで「炭素材料は古い」と言われてきましたが、これらナノ炭素分子の発見により今や年に数千件の論文が出版されるほどの熱狂ぶりで、ノーベル賞も2件出てしまいました。この魅力的な材料の劇的な発見ストーリーを紹介しながらその将来性を紹介します。
No. 71:はやぶさサンプルを分析する
コーディネーター:土`山 明(理学研究科)
実施日:2011年7月30日(土)/ 対象:制限なし
宇宙探査機「はやぶさ」は小惑星イトカワに到着して、いろいろな観測をおこなったのちサンプルを採取しました。サンプルは昨年6月に無事地球に帰還し、今年の1月から初期分析が始まっています。このサンプルが果たしてどのようなものであったのか、みていきましょう。
No. 72:マチカネワニと出会って
コーディネーター:江口 太郎(総合学術博物館)
実施日:2011年8月6日(土)/ 対象:制限なし(親子連れ歓迎)
阪大博物館ではマチカネワニをもっと有名にしようと頑張っています。なぜだと思いますか?大学博物館の標本は、単に展示するだけでなく、いまでも研究や教育に活用されています。いっしょにマチカネワニを探求してみましょう。
No. 73:和古書における"お宝"の見つけ方
コーディネーター:合山 林太郎(文学研究科)
実施日:2011年8月20日(土)/ 対象:制限なし(親子連れ歓迎)
日本の伝統的な様式に則って作られた書物のことを、和本と言います。こうした和本は、博物館や図書館に珍蔵されているだけではなく、町なかの古本屋さんで、今でも入手することができます。ただし、その値段は、五百円からウン百万円まで様々です。これらの和古書は、どのようにしてその値段が決まるのでしょうか。また、そもそも"価値のある本""よい本"とは、何でしょうか。本回では、江戸時代から明治時代までの和古書を見る際のポイントを紹介し、モノ(文化財)を扱うことの楽しさについて解説します。ハマれば、あなたも明日からお宝鑑定団!?
No. 74:絵画のなかの近代大阪をどう"読む"か
コーディネーター:橋爪 節也(総合学術博物館)
実施日:2011年8月27日(土)/ 対象:制限なし
一般に絵画は、美しい芸術作品として鑑賞の対象と考えられています。しかし、個々の作品をどのように味わうかは人それぞれです。今回は、小出楢重や織田一磨などの近代の大阪風景を描いた作品をとりあげ、それを造形的にどう解釈するのか、大阪の歴史や自身の"記憶"を踏まえて何を読み取るかなどを、参加者全員で見たいと思います。
No. 75:形が違えば意味も違う?
コーディネーター:岡田 禎之(文学研究科)
実施日:2011年9月3日(土)/ 対象:高校生以上
日本語の表現を少し入れ替えただけでも意味に違いが生じることは、誰でも経験的に知っていることですが、それは日本語に限ったことではありません。英語の表現も少しの違いが、様々な意味の違いを生み出すことがあります。なぜ意味の違いが生じるのか、ということを表現形式が持っている特徴から考えていければと思います。
No. 76:一般相対性理論入門
コーディネーター:東島 清(理学研究科)
実施日:2011年9月10日(土)/ 対象:制限なし
なぜ地球は太陽の周りを回るのか?太陽が地球を引っ張っているから曲がるのだ。いや、地球は太陽のために歪んだ時間・空間を真っ直ぐに進んでいるに過ぎない。一体どちらが正しいのか。あなたはニュートンの力学的世界観とアインシュタインの幾何学的世界観のどちらを信じるだろうか?
No. 77:生命の仕組みを探る
−いのちの統合的理解を目指す分野の垣根を越えた総力戦−
コーディネーター:野村 泰伸(基礎工学研究科)
実施日:2011年10月1日(土)/ 対象:高校生以上
基礎工学研究科・生体工学領域の教員が中核となって行っている文部科学省グローバルCOEプログラム・大阪大学拠点「医・工・情報学融合による予測医学基盤創成」の研究推進活動を紹介します。当プロジェクトでは21世紀の新しい生命科学・生体医工学をつくる先進的な取組として遺伝子から人体に至る様々なスケールにおける生命機能発現と疾病のメカニズムを統合的に理解し、病気診断や治療予測を可能にする仕組みの構築を目指しています。
No. 78:コーヒーカップのミルクはなぜ混ざる? −流体混合の不思議−
コーディネーター:井上 義朗(基礎工学研究科)
実施日:2011年10月8日(土)/ 対象:高校生以上
コーヒーカップに入れたミルクをスプーンでかき混ぜることは,毎日の生活の中でごく普通に行われ,小さな子供でもできることです.しかし,「なぜ混ざるのか?」と問われるとすぐには答えられない.実際,流体混合を科学的に正確に答えようとするととても難しい問題です.おまけにパラドックス的に見えることがいっぱい.さあ,ありふれた日常生活の中に潜むミキシングの謎を解く旅に,一緒に出かけてみましょう.
No. 79:頼りになる薬剤師:『くすりのいろは』教えます!
コーディネーター:中村勇斗(薬学研究科)
実施日:2011年10月15日(土)/ 対象:制限なし
「風邪、ひき始めには・・・」「つらい肩こり・頭痛には・・・」など、テレビCMでよく耳にする「クスリ」の宣伝ですが、体調不良の時のクスリ選びは大丈夫ですか?薬剤師は病院・薬局だけでなく、学校薬剤師や環境衛生、麻薬・覚醒剤取締りなど広範囲の領域で活動しています。身近な「かかりつけ薬局」の利用法やセルフメディケーション・予防のノウハウを一緒に考えましょう。
No. 80:日本中世の人々と災害
コーディネーター:松永 和浩(総合学術博物館)
実施日:2011年10月22日(土)/ 対象:制限なし
地震、水害、飢饉…。日本中世の人々は自然の脅威に向き合いながら力強く生きてきました。近年の日本史学では、災害史という研究分野が飛躍的に進展しています。ここでは最新の成果を紹介し、災害というわれわれも共有できる地平に立って、過去の人々の経験を振り返るとともに、自らを見つめ直す機会にしたいと思います。
|