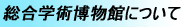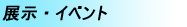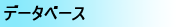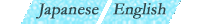サイエンスカフェ@待兼山
大阪大学総合学術博物館で、サイエンスカフェを楽しみませんか。コーヒーを片手にゆったりとした雰囲気で、「科学する」とはどういうことか、研究者とともに考えていきます。それを通して専門家と一般の方々の間のコミュニケーション不全を少しでも改善したいと思っています。お気軽にご参加ください。
| 開催場所: | 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館3階セミナー室 |
|---|
| 開催時間: | 午後2:00〜3:30まで(午後5:00閉館)
ただし、No.83, 84 は午後1:00〜2:30まで |
|---|
| 定 員: | 各回とも30名程度 |
|---|
| 参加費用: | 飲み物代(200円)が必要 |
|---|
| 申込方法: | Webフォーム(申込受付期間確認ページ内のリンクをクリック)、あるいは往復はがき
(カフェ1タイトル、住所、氏名、電話番号、年齢を明記。ご家族でお申込の場合、同伴者のお名前、年齢をご記入ください)を下記宛送付。
〒560-0043 豊中市待兼山町1-13 大阪大学総合学術博物館
http://www.museum.osaka-u.ac.jp/
※「制限なし」のカフェの参加可能年齢は「小学生以上」とさせていただきます。 |
|---|
| 申込期間: | 今期の申込は全て終了しました。
|
|---|
| 共 催: | とよなかサイエンスネット実行委員会 |
|---|
| 協 力: | 大阪大学21世紀懐徳堂 |
|---|
2011年度後期のサイエンスカフェは既に終了しました
No. 81:タンポポが教えてくれること〜「タンポポを通して人間と環境の関係を考える」
コーディネーター:近藤 小百合(薬学研究科)
実施日:2011年12月24日(土) に終了しました
対象:制限なし
春になると咲く黄色い花―タンポポは子どもから大人まで皆さんが知っているでしょう。しかし、タンポポにはいくつかの種類があることを知っているでしょうか。タンポポは種類によって住みやすい環境が違っています。そして、実はその環境に大きく影響しているのは私たち「人間」なのです。「人間」と「タンポポ」、「タンポポ」と「環境」の関係見ていくことで、これからの「人間」と「環境」の関わり方を考えたいと思います。
No. 82:ニュースの作り方
コーディネーター:田村 恒憲(文学研究科)
実施日:2012年1月7日(土)に終了しました
対象:中学生以上
テレビや新聞といった報道機関は日々、ニュースを生産し流通させています。国政与党代表選、株や為替など経済指標の変化、国際紛争、プロ野球のハイライト、季節の風物詩、殺人事件…などなどさまざま。新しく起こったさまざまな「事実」を記述し、伝えることがジャーナリズムの役割ですが、ニュースは事実そのものではない。何をどのようにニュースに仕立て上げるかには一定のパターン(物の見方)があることに気づかれている方も少なくはないでしょう。私が思うに、このパターンというのは、ニュース記事特有の書き方(形式)が影響を及ぼしている部分もあると思われます。出席してくださった方々に実際に基本的な事件や事故記事を書き、「普通の文章」とニュースの形式の違いを体感してもらい、日々何気なく眺めているニュースがいかに特殊な表現であるかを見てもらおうと思います。
No. 83:南部理論と小林―益川理論
コーディネーター:波場 直之(理学研究科)
実施日:2012年1月28日(土)に終了しました
対象:中学生以上
素粒子理論物理学は、湯川先生、朝永先生等日本人がとても活躍している分野です。ノーベル賞を受賞された南部先生と小林・益川両先生の理論を出来るだけ分かりやすく解説します。
No. 84:和の色のガラスを作る
コーディネーター:金森寛・野田雄一(富山大学・富山ガラス工房)
実施日:2012年2月4日(土)に終了しました
対象:制限なし
近年、全国各地にガラス工房ができ、日本人の普段の生活の中にもガラス製品が多く使われるようになってきました。富山市はガラス工芸に力を入れており、世界の中でも有数の規模の工房を設置しています。ガラスの魅力の一つに、陶磁器とは異なる独特の色があります。しかし、色ガラスの原料のほとんどは外国産です。日本には、日本人が好み、日本の文化に合った特有の色、「和の色」があります。日本食やお酒にはやはり「和の色」のガラス食器が欲しいものです。このカフェでは、富山ガラス工房と富山大学理学部が行なってきた「和の色ガラス」の開発についてお話します。
No. 85:「石」のはなし―遠くて近いもの
コーディネーター:伊藤 謙(総合学術博物館)
実施日:2012年2月18日(土)に終了しました
対象:制限なし
皆さんは、「石」と聞くと何を想像しますか?―宝石などの装飾品だけが石ではありません。私たちの身の周りにある金属製品の原料は、石です。しかし、原料をみたことはありますか?石は、化粧品や薬にもなることはご存知でしょうか?このように、石は私達の周りに「身近」に存在していますが、その起源となると多くの人が知らない「遠い」存在でもあります。皆さんとそんな石のふしぎに触れていきたいと思います。
No. 86:知っておきたい生薬の基礎〜同じようで違うもの〜
コーディネーター:東由子(薬学研究科)
実施日:2012年2月25日(土)に終了しました
対象:制限なし
生薬の中には、貴重で高価なために代替品が開発されたものや同じ呼称でも国により基原植物が異なるものがあります。知らずに間違って使用すると、期待する効果が得られなかったり重篤な副作用が現れたりすることがあります。日本薬局方に適合するものが使用されていれば問題はありませんが、旅先だけでなくインターネット等でも海外製品を容易に入手できる今の時代、知っておいていただきたい生薬のお話です。
No. 87:液晶をたのしもう
コーディネーター:久保孝史(理学研究科)
実施日:2012年3月3日(土)に終了しました
対象:中学生以上
液晶と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、携帯電話や、ノートパソコン、壁掛けテレビなどのディスプレイでしょう。実は、そのディスプレイの中にトロトロの液状物質が詰まっているのをご存知でしたか?その物質こそが液晶と呼ばれるものです。液晶は、分子の向きは揃っているのですが、位置に規則性がない特殊な物質で、その特性を活かしてディスプレイに利用されています。そんな液晶の性質を、光学的な特性も交えながら、学んでみましょう。
No. 88:ホタルの光のひみつ
コーディネーター:豊田二郎(総合学術博物館)
実施日:2012年3月10日(土)に終了しました
対象:制限なし
ホタルを素手でとったことがありますか?熱かったでしょうか?いまでは、アニメ映画「火垂るの墓」でしかホタルを知らない人も多いかもしれません。ホタルが光るしくみとまったく同じことを試験管の中で行い、電灯とは違う光(化学発光)の性質と酵素反応について、参加者全員に体験していただきます。
|