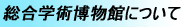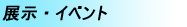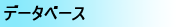�T�C�G���X�J�t�F���Ҍ��R
�@����w�����w�p�����قŁA�T�C�G���X�J�t�F���y���݂܂��B�R�[�q�[��Ў�ɂ������Ƃ������͋C�ŁA�u�Ȋw����v�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��A�����҂ƂƂ��ɍl���Ă����܂��B�����ʂ��Đ��Ƃƈ�ʂ̕��X�̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����s�S�������ł����P�������Ǝv���Ă��܂��B���C�y�ɂ��Q�����������B
�@2013�N�x�O���̃T�C�G���X�J�t�F�͏I�����܂���
�@�ŐV�̃T�C�G���X�J�t�F�͂������������������
| �J�Ïꏊ�F | ����w�����w�p������ �Ҍ��R�C�w��3�K�Z�~�i�[�� |
|---|
| �J�Î��ԁF | ����ߌ�2�F00�`3�F30�܂Łi�ߌ�5�F00�فj |
|---|
| ��@�@���F | �e��Ƃ�20�`30�����x |
|---|
| �Q����p�F | ���ݕ���(200�~)���K�v |
|---|
| ���@�@�ÁF | �L���s������������ |
|---|
| ���@�@�́F | ����w21���I������ |
|---|
No. 108�FDNA����݂Ƃ鐶���i���ƃ����_���l�X
�R�[�f�B�l�[�^�[�F���� �p���i��b�H�w�����ȁj
���{���F2013�N9��7���i�y�j�^�@�ΏہF���Z���ȏ�
���l�Ȑ����킪���ʑc�悩��}������ɂ���Đi�������悤��������킷�̂��u�n�����v�ł��D���݂̂��܂��܂Ȑ������瓾����DNA�z����r����ƁC�����̐������ߋ��ɂǂ̂悤�ɐi�����Ă������\�z�ł��܂��D�i���̉ߒ��ł�DNA�z�����_���ɕω�����ƍl���܂��D���̃����_���l�X�̖@��������m���_�Ɠ��v�w�ɂ��ƂÂ��R���s���[�^�Ōn�����𐄒肷�鐔�w�I���@�ɂ��ďЉ�܂��D
No. 109�F�w�n�C�W�x����w�Ԑ��E�j
�R�[�f�B�l�[�^�[�F�X�{ �c���i���w�����ȁj
���{���F2013�N9��14���i�y�j
�ΏہF���w���ȏ�A�Ƒ��A�ꊽ�}
���Ȃ��́A�u�n�C�W�v��u�}���R�v�������m�ł����H���j���̖�ɕ�������Ă����A�w���E���쌀��x�Ƃ��Ēm�����A�̃A�j����i�́A�����I������J��Ԃ��ĕ�������A���܂ł͐�����Ĉ�����Ă��܂��B���́A���̍�i�̑������A19���I�ȍ~�̐��E�j�̑傫�ȓ����f���Ă��邱�Ƃɂ��C�Â��ł��傤���B����̃J�t�F�ł́A�����Ɂw�A���v�X�̏����n�C�W�x�ɏo�Ă��邳�܂��܂ȃG�s�\�[�h�����ɁA�݂Ȃ���Ɛ��E�j�ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B
No. 110�F覐���킩�鑾�z�n�S�U���N�̗��j
�R�[�f�B�l�[�^�[�F���c �����Y�i���w�����ȁj
���{���F2013�N9��28���i�y�j
�ΏہF���w���ȏ�B���w�����Ƒ��A��͊��}
�F���̎���m��Βm��قǁA���z�n���s�v�c�Ŗ��͓I�ȃV�X�e�����Ǝv���܂��B�Ⴆ�A8�̘f���A���\���̏��f�����قړ��������ɉ�]���Ă���������B���f�ƃw���E�����听���i98���ȏ�j�̍L���ȉF����ԂŁA2���ȉ������Ȃ��S��P�C�f��}�O�l�V�E����_�f���Z�k���āu�v�̒n�����ł����s�v�c���B�u�قړ����ޗ������v����u�قړ��������v�ɘf�����ł����ɂ��ւ�炸�A�n���ɂ����C�����萶�����h���Ă����n���̃��j�[�N���B�������̌����O���[�v�ł́A���ʑ̌����������g����覐�A�|���������ׂĂ��܂����B覐̍ŐV�̕��͂���킩���Ă������z�n�̗��j�ɂ��ĉ�����܂��B
No. 111�F�����q�A����ĐG���Ď��̌�
�R�[�f�B�l�[�^�[�F�R�� �_���i���w�����ȁj
���{���F2013�N10��5���i�y�j
�ΏہF���w���ȏ�A���w�������l�܂ŁA�Ƒ��ŎQ�������}
���B�̐g�̂܂��ɂ͑@�ہA�S���A�v���X�`�b�N��h���ȂǁA�l�X�ȁu�����q�v�����������Ă���A���B�̓��퐶���ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��B�����q�����猻���@�\������܂��B���̃T�C�G���X�J�t�F�ł͎��ۂɂ����Ƃ����Ԃɂł��Ă��܂������q�����������܂��B����̓[���[�̂悤�ȍ����q�B��]�������ɂ́i�l������ł����j���ۂɂ��̍����q����̌����Ă����������Ǝv���Ă��܂��B���Ċy�����A�G���Ċy�����f�G�ȃI���W�i���|�p�i�������q�ō���Ă݂܂��B�ȒP�Ȏ�������ŋ߂̍����E���̍����q��p���������Ő�[�܂ł���C�ɂ��Љ�����܂��B
No. 112�F���w���Ă���Ȃɂ������낢 �[�g�Ђ��ƕ��G�n�̘b
�R�[�f�B�l�[�^�[�F�� �p�q�i���w�����ȁj
���{���F2013�N10��12���i�y�j
�ΏہF���Z���ȏ�
�F�����, ��w�̐��w�̌����Ƃ����Ɖ����v�������ׂ܂���?
����v�Z? �������, ��₱�����v�Z�����܂���, �������ł͂���܂���.
���̃��N�`���[�ł̓g�|���W�[����̈�̌����Ώۂł��錋�іځE�g�Ђ��ɂ���, ������
�͊w�n����̌����Ώۂł���J�I�X�E�t���N�^���ɂ���, �ŋ߂̘b��������Ȃ���ł��邾���킩��₷�����b���܂�.
�����̗��ʂ���, ���w���ǂ̂悤�ɔ��W���Ă����̂�, ���w���ǂ̂悤�Ɏ������̐�����``���ɗ���"�̂�,
�F����ɂ��`���������Ǝv���Ă��܂�.
|