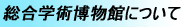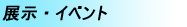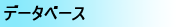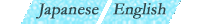小学校連携科学体験教室
主催:豊中市社会教育活性化推進委員会
大阪大学総合学術博物館
共催:大阪大学大学教育実践センター
時期:2006年3月1日〜3日、7日、9日〜10日
平成18年3月1日から10日の間、豊中市社会教育活性化推進委員会が行っている事業「社会教育活性化21世紀プラン」の一環として、豊中市教育委員会と大阪大学が連携して小学校連携科学体験教室を実施した。この授業は、理科離れが指摘されている子どもたちに理科に対する興味をもってもらうことを目的として計画されたものである。授業には豊中市内の6つの小学校の生徒が計450名参加した。
授業は、昨今周辺にある様々な自然現象などに対して興味を失い無関心になっているといわれる子どもたちに、解剖や実験を通して物事を観察すること・考えることを身に付けてもらうことに主眼を置いて行われた。授業の最後に行われる質問コーナーでは生徒たちから多数の質問があり、関心の高さがうかがわれた。
また、授業の前後にはイ号館と待兼山修学館の展示室を見学した。

「タコを解剖してみよう」
|

「自然世界に見る回転運動」
|

「ペットボトルで地震の液状化現象を観察しよう」
|

「水を吸う高分子」
|
科学体験教室内容
| 1. |
「タコを解剖してみよう(動物の解剖から多様性と共通性を見る)」
庄内小学校 5年生 66名
講師:古屋 秀隆(理学研究科・生物)
無脊椎動物であるタコを解剖することによって、脊椎動物であるヒトとの共通点や違いを知ってもらい、なぜそのような違いや共通点があるのかを考えてもらった。
|
| 2. |
「温度で変わるものの性質」
千成小学校 6年生 57名
寺内小学校 4年生 68名
講師:江口 太郎(総合学術博物館)
テニスボールやバナナ等私たちの身近にあるものを液体窒素を用いて凍らせ、その結果ボールが大音響で破裂したり、バナナがきれいに2つに折れたりする様子を観察してもらうことで極低温の世界を実感してもらった。
|
| 3. |
「自然世界にみる回転運動」
大池小学校 5年生 137名
講師:藤田 佳孝(理学研究科・物理)
「回転運動」のもつ様々な特徴をいくつかの用具を用いて実際に体感してもらい、それらの特徴を利用して作られている身近なもの(自転車や自動車)を紹介した。更に身近なものだけでなく、太陽や銀河など宇宙にあるものも回転していることに目を向けてもらった。
|
| 4. |
「ペットボトルで地震の液状化現象を観察しよう」
庄内西小学校 5年生 66名
講師:谷 篤史(理学研究科・宇宙地球科学)
地震がおこった時に固い地面が液体のようになってしまう現象(液状化現象)はなぜ起こるのかを、砂と画鋲が入ったペットボトルを使用した実験を通して考えてもらった。
|
| 5. |
「水を吸う高分子−吸水性ポリマーの不思議−」
南丘小学校 6年生 56名
講師:上田 貴洋(総合学術博物館)
吸水性ポリマーと呼ばれる多量の水や液体を吸収する性質を持ったプラスチック(高分子材料)を用いた実験を通して、自分の目で観察して考える習慣を身に付けてもらった。
|
|