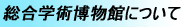  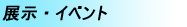 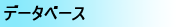  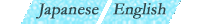 |
このサイエンスカフェは、すでに終了しています。 最新のサイエンスカフェは、こちらをご覧下さい。 サイエンスカフェ@待兼山"土曜の午後はミュージアム"土曜日の昼下がり、大阪大学総合学術博物館でサイエンスカフェを楽しみませんか。 サイエンスカフェは、いわゆる「講演会」や「何でも相談室」といったようなQ & A方式で専門家が「正解」を教える場所ではありません。 正解は得られないかもしれません。コーヒーを片手にケーキをつまみながら「科学する」とはどういうことかを、専門家とともに考えていきます。 そのことを通して専門家と一般の方々の間のコミュニケーション不全を少しでも改善できれば、サイエンスカフェとしては成功だと思います。 大阪大学の総合学術博物館、大学院理学研究科、大学院基礎工学研究科の教員有志がコーディネーターを務める予定です。
No. 1:「携帯電話の電波は体に悪い?」 コーディネーター:江口太郎 実施予定日:2008年4月5日 対象:中学生以上一般の方 内容: 最近、新聞で「携帯電話の電波は体に悪い?」というような記事を目にしました。皆さんはどう考えるでしょうか。じつは、目に見える光(可視光線)も電波の一種です。自然界にはいろいろな波がありますが、その中でも代表的な「電波」について、皆さんといろいろ考えていきます。けっして医学的な相談会ではありません。科学の考え方を双方向の会話で楽しむことを目指します。 No. 2:「エネルギーのこれから」 コーディネーター:池田茂 実施予定日:2008年4月12日 対象:中学生以上一般の方 内容 現在の便利で豊かな生活をささえるエネルギーのほとんどは、石油などの化石資源からとりだされているのはご存知でしょう。このような生活を、わたしたちはこれから先もつづけていけるのでしょうか?つづけていくには、どんな条件が必要になってくるのでしょうか?そもそもエネルギーってのは、どんなもので、どんなふうにつきあっていけばよいのでしょうか?化石資源とべつのエネルギー、たとえば太陽エネルギーは本当に有効なの?ここでは、エネルギーの今と未来についてみなさんと考えてみたいと思います。 No. 3 :「論理とパラドクスの迷宮への誘い」 コーディネーター:藤原 彰夫 実施予定日:2008年4月19日 対象:誰でも OK 内容: あなたは論理に強いですか? では,簡単なテストをしてみましょう.ここに4枚のカードがあります.それぞれのカードの表にはアルファベット,裏には自然数が書かれています.今,机の上にこの4枚のカードが置いてあって,それぞれ A, B, 3, 4 と書かれています.このとき「母音の文字の裏には奇数が書かれている」という主張が正しいかどうか確かめるために,最低限,どのカードをめくってみる必要がありますか? (この問題に対し,大学生の80%以上の人たちが A と 3 のカードをめくると答える,という報告があります.もちろん正解は A と 4 ですね.) 論理的思考は正しい推論を行う上で欠かせない作業です.しかしながら,正しい推論を行ったつもりなのに,時として常識からかけ離れた結論に導かれることがあります.これは,単なる勘違いの類いから,人間の理性の本質に深く関わる深遠なパラドクスまで様々あります. このサイエンスカフェでは,そうした論理とパラドクスの世界を,皆様と一緒に旅してみたいと思います. No. 4:「防犯カメラはどこまで見張る?」 コーディネーター:佐藤 宏介 実施予定日:2008年5月10日 対象:高校生以上一般の方 内容: 防犯カメラが設置されていない銀行やコンビニエンスストアは今日まずありません。犯罪とは無縁でプライバシーがある我々には無用なものです。しかし、新製品のデジタルカメラに搭載されている顔を認識する技術を防犯カメラに用いれば、個人が瞬時に特定できるようになってゆきます。もう数年すれば、コンピュータは皆さんがどこを散歩し、どの広告塔を見たかまで認識することができるようになるかもしれません。このような技術はどこまで許されるか、どこまで許すのか、皆さんと一緒に考えてゆきたいと思います。 No. 5:「古文書でたどる待兼山」 コーディネーター:廣川和花 実施予定日:2008年5月24日 対象者:高校生以上一般の方 内容: <サイエンス>としての歴史の研究では、研究者は古文書と格闘します。「くずし字」などをどのようにして読み解くのでしょうか? たとえば、大阪大学総合学術博物館の裏手にひろがる待兼山は、古来、歌枕として名高く、『枕草子』にもその名がみられます。また、ふもとの村々にとって待兼山は、肥料や薪を得るための「入会山」として重要な場所でした。待兼山に関する古い文献や古文書を実際に読んでみて、そこにえがかれた待兼山の歴史に皆さんと一緒に触れてみたいと思います。 No. 6:「水道水はそのまま飲めない?」 コーディネーター:文珠四郎秀昭 実施予定日:2008年6月7日 対象者:高校生以上一般 内容: 日本の水道水の水質基準は法律により厳しく規制されていて、その安全性も保障されています。しかし、ミネラルウォーターなどのボトル水を買って飲む人、またこれを炊事に使う人たちが増えてきており、その消費量は年々増加しています。これに対し、水道水をそのまま飲む人が減ってきているように思われます。なぜこのような風潮になっているのでしょう。 このサイエンスカフェでは、私たちの最も身近にある「水」をテーマにして、日常生活における「科学的な」考え方について議論したいと思います。ちなみにこのサイエンスカフェは、特定の水が体に良い悪いといった判定をする場ではありません。 No. 7:「クスリに好奇心:生薬なるほど物語」 コーディネーター:高橋京子 実施予定日:2008年6月21日 対象:高校生以上一般 内容: 生薬は「生きた薬」です。生きているからこそ日々変化し、多様です。生薬の基源は、長い歴史の中でさまざまに変遷し、現在に至ります。日本古来の文化に培われ進化してきた漢方薬も、複数の生薬から組み立てられています。薬食同源である生薬を知り日常に応用すれば、長期的な健康維持に役立ちます。身近に生える植物の意外な効果に好奇心を持ち、五感を刺激する体験を通して、食べ物であり薬でもある生薬の不思議と活用について一緒に考えましょう。 No. 8:「身の回りのものをつくっているものはなあに?―分子の大きさを実感する方法を考えよう!」 コーディネーター:上田貴洋 実施予定日:2008年7月5日 対象:小学5,6年生のお子様とその保護者の方 内容: 世の中のいろいろな「物」は何からできているのでしょう。例えば、角砂糖を考えて見ましょう。角砂糖を小さく、小さく分けていくと最後はどんな大きさの粒になるのでしょう?みなさんの身の回りの「物」をつくっている粒の大きさを実感するにはどうすればよいのでしょうか?みなさんの一緒に考えてみたいと思います。 No. 9:「宇宙から極微の世界まで −自然界に働く四つの力−」 コーディネーター:藤田 佳孝 実施予定日:2008年7月19日 対象:高校生以上一般の方 内容 宇宙から極微の世界まで・・・見た目の多様さとは異なり、自然界は驚くほど単純で基本的な要素の組み合わせで出来ているようです。たとえば、おおもとの力(相互作用)は、重力、電気磁気の力、弱い相互作用、強い相互作用の四つしかありません。つまり大宇宙から原子核、クオークの極微の世界まで、自然界全体が、四つの力の働きのバランスで成り立っているのです。 現実に目の前に感じる重力や電気、磁気の力からはじめ、人類が認識しているより大きな世界:星、銀河、宇宙、またより小さな世界:分子、原子、原子核、クオーク、そのような世界を組み立てるおおもととなっている四つの力について、しばし思いを馳せてみませんか。 No. 10:「ネットワークとうまくつきあう」 コーディネーター:豊田二郎 実施予定日:2008年8月2日 対象:中学生以上一般の方 内容: 最近は、テレビCMや車内広告等でも「続きはWebで!」とか、「○○で検索↑」、など、インターネットでアクセスするのがあたりまえのようになってきています。パソコンや携帯電話から列車や飛行機、コンサートのチケットを取ったり、銀行振り込みができるのも日常の出来事となっていますし、毎年3月15日が近づくと頭を痛める確定申告の書類もWebから作成するようになってきています。ネットワークは道具として非常に便利な反面、フィッシング(なりすまし)詐欺や、迷惑メール、ウイルス被害など影の部分も大きくなってきています。ネットワークと上手につきあうための方法をみなさんとともに考えましょう。 No. 11:「データによる論証とは:データの見方,考え方」 コーディネーター:狩野 裕 実施予定日:2008年8月9日 対象:特に制限なし 内容: 新聞や雑誌など多くのメディアでは,尤もらしいデータを添えた論証が多く見られます.私たちはそのような主張をどのように考えればよいのでしょうか.たとえば,(1) カップ麺やスナック菓子の摂取は非行を助長する,(2) TV視聴率は信用できる? (3) タバコを吸うと肺がんになり易い,(4) 子のつく名前の女の子は頭がいい,などなど.日本人は,このような主張を鵜呑みにするタイプと頭から否定するタイプとに分かれるようです.みなさんはどちらに近いでしょうか.今回のカフェでは,このような巷にあふれるデータつきの論証をどのように考えるべきか,お越しになった皆さんと一緒に考えてみたいと思います.そこには,メディアや執筆者の力量,そして,思惑が見え隠れします. No. 12:「口になるか、肛門になるかが、動物の分かれ目」 コーディネーター:古屋秀隆 実施予定日:2008年8月23日 対象:特に制限なし 内容: 動物の仲間は大きく2つのグループに分けられます。1つは、発生の初期にできるある凹みが将来の口になるグループ、もう1つは、その凹みが肛門になるグループです。前者は昆虫を頂点とするグループ、後者は我々ヒトを含む脊椎動物を頂点とするグループです。発生の過程でできる単なる凹みが、将来食べ物が入る入口となるか、食べ物を消化した後の出口となるかの違いですが、これが動物の進化の上で大きな分かれ道となっています。動物の進化の歴史を一緒に考えてみましょう。 No. 13:「体の中の精密機械」 コーディネーター:荒木 勉 実施予定日:2008年8月30日 対象:特に制限なし 内容: 究極の精密機械は生体だと言われています。ですから生体を理解することは、あたらしい機械設計や機能材料のいいヒントになるかもしれません。そこで機械の視点でわれわれ自身の体の仕組みを考えてみましょう。 精密な機械が配置されて、しかもその設計が物理工学的に理にかなっていることに驚きます。ただ、われわれの体はとほうもなく複雑で膨大な部品からなっているので、限られた時間では一部しか取り上げることはできません。今回は「耳」や「目」、「心臓」、「血管」など比較的分かりやすい部分を取り上げて、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。だれがこのような機械を設計したのか、不思議な世界です。 |

