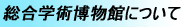  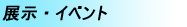 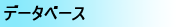  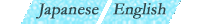 |
サイエンスカフェ@待兼山(2009年後期)"土曜の午後はミュージアム"阪大博物館のサイエンスカフェも2年目を迎えました。昨年は初めての経験で手探りで始めましたが、おかげさまで大好評でした。コーヒーを片手にクッキーをつまみながら「科学する」とはどういうことかを、研究者とともに考えていきます。そのことを通して専門家と一般の方々の間のコミュニケーション不全を少しでも改善したいと願っています。 大阪大学の総合学術博物館、理学研究科、基礎工学研究科、文学研究科の教員や院生有志がコーディネーターを務める予定です。
コーディネーター:深川 聡子 (大学院文学研究科) 2009年12月19日 対象:制限なし・親子連れ歓迎(国語辞典の冊子体が必要) 内容: しり取り、逆さ言葉、数え歌、俳句…日常使っている言葉に、何らかのルール=制約をあてはめることで遊びが生まれることを、私たちは経験的に知っています。1960年フランスで発足した「ウリポ(潜在的文学工房)」の作家たちは、ルールに則った文学創造をきわめて意識的におこなってきました。彼らのさまざまな創作の技法を紹介し、彼らにならって実際にことばで遊んでみたいと思います。 No. (39):太陽系外に生命は存在するか? コーディネーター:芝井 広 (大学院理学研究科) 2010年1月9日 対象:高校生以上 内容: 太陽系外の惑星がすでに300個以上、発見されている。これらの惑星のほとんどは、太陽系の惑星と似ても似つかぬものであり、生命活動が存在することを示唆する証拠はない。はたして生命が存在する星は地球以外にあるのだろうか。 No. 40:シルクロードと日本 コーディネーター:坂尻 彰宏 (大学院文学研究科) 2010年1月16日 対象:中学生以上 内容: ユーラシア大陸の各地を縦横に結びつけていた「シルクロード」は、日本にも大きな影響を与えていました。シルクロードの交通・交易が盛んに行なわれ、遣唐使などを通じて日本と大陸との交流もみられた中国の唐時代を中心に、日本とシルクロードとのかかわりについて、最新の研究成果も交えてお話しします。 受付を2010年1月7日(木)まで延長します。 お申込頂いた時期によっては、当否の連絡が、2010年1月4日(月)以降になる場合もございます。 No. 41:馬形埴輪はなぜ復元できたのか? コーディネーター:寺前 直人 (大学院文学研究科) 2010年1月23日 対象:高校生以上 内容: 博物館などで見かける考古資料のなかでも、土器や埴輪には、欠損部分を石膏などで補填した復元品をみかけることがあります。 これは考古学者の思いつき?それとも想像でしょうか?今回は出土品の復元方法やその根拠について、総合学術博物館に展示している待兼山5号墳出土の馬形埴輪を題材に紹介していきます。 No. (42):いろいろな電池 コーディネーター:川野 聡恭 (大学院基礎工学研究科) 2010年1月30日 対象:制限なし 内容: 地球に優しいエネルギーに関連して注目されているリチウムイオン二次電池、太陽電池および燃料電池などの動作原理を簡単に説明します。また、果物電池を用いたデモンストレーションも予定しています。 当否の連絡は、2010年1月4日(月)以降になります。 No. 43:弁証法の魅力 コーディネーター:家高 洋 (大学院文学研究科) 2010年2月13日 対象:高校生以上 内容: 古代ギリシア以来、弁証法は西洋哲学の基本的な考え方の一つです。ヘーゲルまでの弁証法の歴史をたどりつつ、みなさんといっしょに弁証法的に考えることを通じて、その魅力を味わってみましょう。 No. 44:大学博物館を考える コーディネーター:横田 洋 (総合学術博物館) 2010年3月6日 対象:制限なし 内容: 近年、大学付属の博物館が増えていますが、そもそも大学博物館の役割とは何でしょうか?一般の公立・私立の博物館と何が異なるのでしょうか?学生にとって、研究者にとって、そして一般の来館者にとって、「大学の」博物館はどのようにあるべきでしょうか?大学博物館について語り合いましょう。 No. 45:ホタルの光のひみつ コーディネーター:豊田 二郎 (総合学術博物館) 2010年3月13日 対象:制限なし 内容: ホタルを素手でとったことがありますか?熱かったでしょうか?いまでは、アニメ映画「火垂るの墓」でしかホタルを知らない人も多いかもしれません。ホタルが光るしくみとまったく同じことを試験管の中で行い、電灯とは違う光(化学発光)の性質と酵素反応について、参加者全員に体験していただきます。 No. 46:磁石と電波でからだをみる? コーディネーター:江口 太郎 (総合学術博物館) 2010年3月20日 対象:中学生以上 内容: 電波といえば、テレビ、ラジオ、携帯電話などが頭に浮かびます。磁石といえば、メモ用紙を冷蔵庫などにとめるマグネット、ピップエレキバンなどでしょうか。その二つを組み合わせて、どのようにして人体を観るのか。最近病院で導入されているMRIについて、考えてみたいと思います。 ( )つきのカフェ番号は豊中市との共催です。 |

