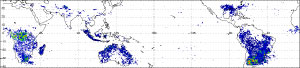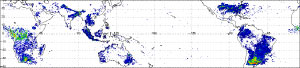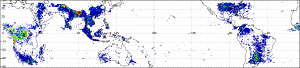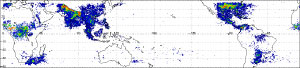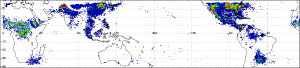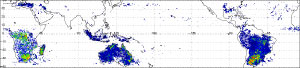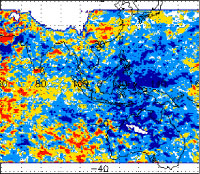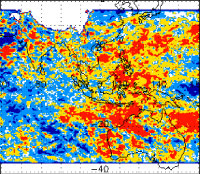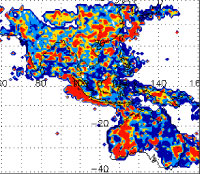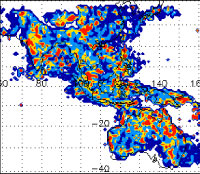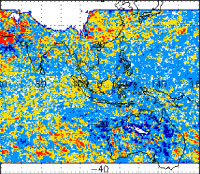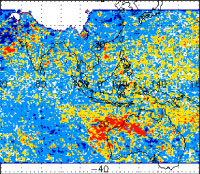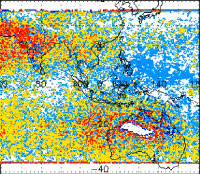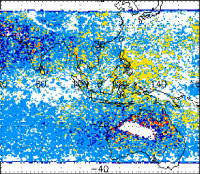| 1. |
変わる里山:北摂の絵図と地図にみる景観変化 | |
| |
||
| |
||
| 3. |
物質科学へのアインシュタインの功績 | |
| 4. |
この世で最も重い原子を求めて |
|
| |
漢方薬ナビゲーション:時空を超えて科学する心 | |
| |
||
| 6. |
宇宙から見た世界の雷活動 |
|
| 7. |
太陽エネルギーの有効利用 |
|
| 8. |
繰り返しから生まれる複雑さ |
|
| 9. |
ナノテクの4次元空間=ナノ3次元+アト秒 | |
| |
||
| 10. |
PDBj: Protein Data Bank japan (日本蛋白質構造データバンク) | |
| 11. |
時を止め、空間を作る |
|
| |
||
| 12. |
琥珀にひそむ時空のなぞ |
|
| 13. |
時間と空間の知覚:知と行動の科学 | |
| |
||
| 14. |
曲面の世界 |
|
| |
||
| 15.
|
出版活動 |
|
6.
宇宙から見た世界の雷活動 |
||
工学研究科/森本健志・河崎善一郎 |
||
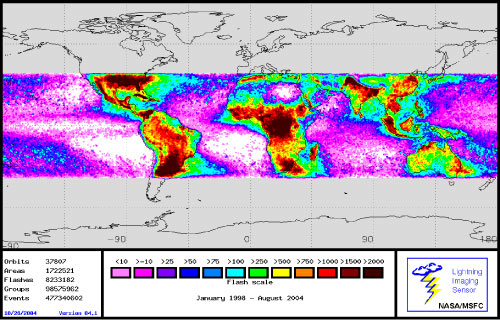 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得された観測データをより詳細に考察すること、正確な地球環境観測を継続して行くことは、これからも地球で暮らしていく私にとってとても重要なことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
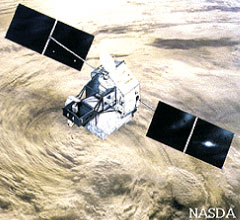 1997年11月28日に打ち上げられた熱帯降雨観測衛星(TRMM)には降水を宇宙空間から測定するレーダ(PR)、雷活動を測定するセンサー(LIS)など、5つのセンサーが搭載され、南緯35度から北緯35度の雷嵐活動を測定しています。
1997年11月28日に打ち上げられた熱帯降雨観測衛星(TRMM)には降水を宇宙空間から測定するレーダ(PR)、雷活動を測定するセンサー(LIS)など、5つのセンサーが搭載され、南緯35度から北緯35度の雷嵐活動を測定しています。